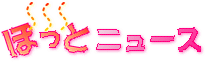 |
||
| 初めてのミカン狩り (令和7年12月7日) みかんの様子をホットニュース84に書いてからおよそ50日、今日は令和7年12月7日ですが、直径7㎝ほどに実ったみかん1個を試食しました。女子職員にも一緒に試食してもらいましたが、まあまあの味でした。今日の生活塾7班は2年生3年生合わせて12名で、若菜小、上穂波小、飯塚小の3小学校からの参加でした。この日、初めてのミカン狩りをしました。午前中の体験活動で里芋の収穫とイモ洗い棒を使った皮むき体験をしました。その後、小粒のみかんの収穫体験をしました。ミカン狩りと言ってしまうと「小みかん」ですから少し大げさですが、小さなみかん1人1個あてということにして収穫体験をしました。子どもの中には、もう1個食べたいというリクエストがきましたので、みかんの味としては悪くなかったようです。植えてから5年目(令和3年3月定植)のみかんですが、子どもと初めてのミカン狩りを楽しみました。 |
87 |
|
| 学んだイモの掘り方 (令和7年11月6日) 令和7年11月6日、菰田保育所の5歳児40名が芋掘りにやってきました。あらかじめ立ててある園名札の畝を掘るのが通例ですが、掘る畝の変更申し出がありました。菰田保育所は例年、生活体験学校で収穫したイモの全量を石焼きイモ(園庭での)にして園児に食べさせます。石焼きイモにするサイズは大き過ぎても小さ過ぎても良くない、程よい大きさがあります。つまり、隣り合わせの畝を掘って似たようなサイズの芋を掘るよりも畝を選んで程よい大きさの芋をバランス良く掘って帰りたいとう希望だったのです。そんな知恵を学んだ場面があったのです。それは、つい何日か前に生活体験学校で開かれた保育者体験講座でした。この体験講座は保育士がわが子と一緒に生活体験学校の体験学習を楽しむという催しです。この講座に菰田保育所の保育士数人が参加して、今年のイモ畑の作、不作の実情を学習済だったのです。選んで掘った畝の芋を積んで、送迎観光バスに乗り込んで帰る園児と保育士の笑顔ははじけていました。 |
86 | |
| いもほり、始まる (令和7年11月4日) 令和7(2025)年度のサツマイモの収穫はあまり期待できません。今年は6月の終わりまで日照り続きでした。桜が丘幼稚園(41名)が苗植えにやってきたのは6月27日(金)でした。この日、二番苗を切り取って植えてはみたものの、活着するのは期待薄という日照りでした。続きの28日も7月3日も水やりをしましたが、焼け石に水という感じでした。両日とも枯れた苗を抜いては5本、また5本と補植してみました。心配のし通しで、9月下旬の雨に僅かの望みを抱き、10月に入っての雨に望みをつなぎました。10月11日、7株ほどの試し掘り、10月17日に横田こども園の芋掘りが一番早い収穫でした。去年の記録では、10月10日の飯塚東保育園が一番早い収穫でしたから、7日ほど遅い収穫になりました。実入りを心配しながらの収穫開始です。 |
85 | |
待たれるのは、みかんが色づく頃 (令和7年10月17日) 平成3年3月、温州ミカン10本を植えましたが、生育は今ひとつという状況です。ひとつには、令和6年1月、みかんとブルーベリーを移し替えたのがブレーキになっています。今現在、ブルーベリーは動物小屋南の小広場に16本植わっています。移し替えたミカンの現状は、正門北に1本、国旗掲揚台周辺に2本、その南に4本、合計7本植わっています。南の4本にはテニスボールほどの4個のみかんが実っています。この7本の南に3本のみかんが植わっています。3本のうちの1本は小みかんです。小粒のみかんがびっしりついていて、枝が地面にこするほど垂れ下がっています。一番南の1本が最も多くの実をつけていて、30個は優に超えている模様です。全部合わせてミカンの総本数は10本です。みかんが色づいて、やがて子どもの口に入る日が待たれます。 |
84 | |
クリ拾いの季節がやってきた (令和7年9月7日) 今年もクリ拾いの季節がやってきました。9月2日(火)に300個拾いました。9月6日(土)には180個拾い、その後20個ぐらい追加して拾いましたので、合わせて約200個拾いました。180個の大半は幼児6人と保育士、保護者合わせて5人の計11人でお持ち帰りにしました。去年の記録を見てみましたら、9月2日に100個、9月3日に114個とありましたので、時期的には去年今年とあまりずれていないようです。9月2日に拾った分の40個余りはクリご飯用に使いました。9月7日、クリご飯は生活塾第4班の2・3年生13名に提供しました。クリご飯は、塩、昆布、料理酒で味付けしました。クリご飯の外に、ゆでクリにして一人2個あて食べさせました。この日の参加者は思わぬご馳走にあずかったことでした。同時に、第4班の13名はクリ拾いをこの日新たに体験しました。 今年もクリ拾いの季節がやってきました。9月2日(火)に300個拾いました。9月6日(土)には180個拾い、その後20個ぐらい追加して拾いましたので、合わせて約200個拾いました。180個の大半は幼児6人と保育士、保護者合わせて5人の計11人でお持ち帰りにしました。去年の記録を見てみましたら、9月2日に100個、9月3日に114個とありましたので、時期的には去年今年とあまりずれていないようです。9月2日に拾った分の40個余りはクリご飯用に使いました。9月7日、クリご飯は生活塾第4班の2・3年生13名に提供しました。クリご飯は、塩、昆布、料理酒で味付けしました。クリご飯の外に、ゆでクリにして一人2個あて食べさせました。この日の参加者は思わぬご馳走にあずかったことでした。同時に、第4班の13名はクリ拾いをこの日新たに体験しました。 |
83 | |
| 止まらぬイモ畑の草丈 (令和7年8月26日)
今年のサツマイモ畑は昨年とは様子が違いました。6月の終わり近くまで続いた雨模様が途切れた途端に、連日の日照りが始まりました。6月下旬に植えた二番苗のサツマイモは、根付くどころか切れ目ない猛暑に耐えきれませんでした。青息吐息の苗をなんとかしようと、令和7年7月4日、ひまわり幼稚園がイモ畑の草取りにきました。そして、翌月の8月26日には、再び、ひまわり幼稚園の職員2名が草取りにやってきました。焼けつくような日照りの畑で続いた草取り作業でした。以前に刈り取られた草が続いた日照りの熱でしっかり乾燥していました。その枯れ草を片づけなければ、新たに伸びてきた青草を刈りとらなければいけません。この日の朝、片付けた乾燥草はリヤカー8台分もありました。1時間と少しの作業になりましたが、汗だくになりました。熱波に押され、生い茂る草に攻められて、今年のサツマイモの収穫が思いやられる8月です。 |
82 | |
| 8月最後の生活塾 (令和7年8月24日) 令和7年8月24日、生活塾第3班が実施されました。8月最後の体験活動です。今回の合宿参加者は2~3年生14名で、所属校は穂波東小、頴田小、椋本小の3小学校でした。今回の昼食でもそうめん流しをしました。薬味はネギ、ショウガ、ミョウガが用意されました。ミョウガは生活体験学校の菜園で収穫したものです。わかめとシャケをまぜたおにぎりも準備しました。なすび、ゴボウ、カボチャは生活体験学校で収穫したものです。野菜3種は衣をつけて天ぷらにしました。ゴボウとカボチャは、天ぷらとは別に衣をつけずに「素」で揚げたものを用意しましたので、合わせて5種類の野菜の献立になりました。そうめんとおにぎりと油を使った5種類の野菜料理という豪勢な昼食になりました。8月の終わりをしめくくる生活塾でした。 |
81 | |
| 初めてのスイカ栽培 (令和7年8月5日) 生活体験合宿第5班が、令和7年8月2日から1泊2日の日程で実施されました。この日、夏野菜がたくさん使われました。生活体験学校の南と北の菜園で収穫された野菜です。ニンジン、ナス、キュウリ、ジャガイモ、スイカ等々です。ジャガイモは6月21日に収穫  した約100㎏のジャガイモの一部です。ナスが南の菜園に2畝植えてあります。1畝には21本、もう1畝には24本のナスが植えてあり、やがて秋ナスとして食される小ぶりのナスの実が沢山ついています。今年初めて栽培したスイカを収穫しました。子ども達は冷蔵庫で冷やしたスイカが甘くて美味しいと大喜びしました。スイカ苗は6月17日に3本植えました。その後別に育てた苗2本を植え足しましたので、合計5本のスイカ栽培でした。次のスイカは、8月9日からの体験合宿第6班の子ども達に食べさせる予定です。 した約100㎏のジャガイモの一部です。ナスが南の菜園に2畝植えてあります。1畝には21本、もう1畝には24本のナスが植えてあり、やがて秋ナスとして食される小ぶりのナスの実が沢山ついています。今年初めて栽培したスイカを収穫しました。子ども達は冷蔵庫で冷やしたスイカが甘くて美味しいと大喜びしました。スイカ苗は6月17日に3本植えました。その後別に育てた苗2本を植え足しましたので、合計5本のスイカ栽培でした。次のスイカは、8月9日からの体験合宿第6班の子ども達に食べさせる予定です。 |
80 | |
酷暑の中のソーメン流し (令和7年8月2日) 令和7年8月2日から1泊2日の日程で、生活体験合宿第5班が実施されました。連日38℃、39℃という気温が続きます。今回の合宿参加者は4~6年生14名で、所属校は上穂波小、伊岐須小、日新館小、片島小の4小学校でした。午前中の活動で箸作りをしました。竹を素材に「自分の箸」を作り、それぞれの名前を書き込みました。その後、おにぎり作りをして、茹でてもらったソーメンで「ソーメン流し」を楽しみました。生活体験学校のソーメン流しのセットの素材は、竹ではなく檜(ヒノキ)です。竹で作ると次の年には新しく作り替えなければいけませんが、ヒノキだと何年も使えます。薬味には生活体験学校の畑の大葉が使われました。流れてくるソーメンにマイ箸を突っ込んで、掬(すく)い上げては食べました。ソーメンが終わったところで、ミカンとパインの缶詰、ゼリーを流してもらって子どもたちは大喜びしました。酷暑の夏の「ソーメン流し」でした。 令和7年8月2日から1泊2日の日程で、生活体験合宿第5班が実施されました。連日38℃、39℃という気温が続きます。今回の合宿参加者は4~6年生14名で、所属校は上穂波小、伊岐須小、日新館小、片島小の4小学校でした。午前中の活動で箸作りをしました。竹を素材に「自分の箸」を作り、それぞれの名前を書き込みました。その後、おにぎり作りをして、茹でてもらったソーメンで「ソーメン流し」を楽しみました。生活体験学校のソーメン流しのセットの素材は、竹ではなく檜(ヒノキ)です。竹で作ると次の年には新しく作り替えなければいけませんが、ヒノキだと何年も使えます。薬味には生活体験学校の畑の大葉が使われました。流れてくるソーメンにマイ箸を突っ込んで、掬(すく)い上げては食べました。ソーメンが終わったところで、ミカンとパインの缶詰、ゼリーを流してもらって子どもたちは大喜びしました。酷暑の夏の「ソーメン流し」でした。 |
79 | |
| ミニトマトとブルーベリーの初物 (令和7年7月6日) 令和7年7月6日、生活塾第2班が実施されました。直前のキャンセルもあって、11名の参加  者でした。所属の学校は、庄内小、鯰田小、上穂波小、頴田小、幸袋小の5校からでした。この日の野外活動はブルーベリーの収穫とミニトマトの試食でした。ブルーベリーの実をカラスが狙っているという情報も入っていましたので、熟れている果実だけでも子どもに食べさせたいと収穫しました。木が若いので果実が小さくて残念でしたが、1人2個あて収穫して食べました。ミニトマトは黄色と赤色の2種類で形も良く、味も甘くて大変好評でした。去年のミニトマトは失敗でしたが、今年は植え方を工夫しネットもしっかり張って、去年の失敗を克服して成功でした。ミニトマトもブルーベリーも共に初物でした。 者でした。所属の学校は、庄内小、鯰田小、上穂波小、頴田小、幸袋小の5校からでした。この日の野外活動はブルーベリーの収穫とミニトマトの試食でした。ブルーベリーの実をカラスが狙っているという情報も入っていましたので、熟れている果実だけでも子どもに食べさせたいと収穫しました。木が若いので果実が小さくて残念でしたが、1人2個あて収穫して食べました。ミニトマトは黄色と赤色の2種類で形も良く、味も甘くて大変好評でした。去年のミニトマトは失敗でしたが、今年は植え方を工夫しネットもしっかり張って、去年の失敗を克服して成功でした。ミニトマトもブルーベリーも共に初物でした。 |
78 | |
ジャガイモ収穫、123㎏ (令和7年6月23日) 令和7年6月20日、あさひ保育園の5歳児がジャガイモの収穫体験にきました。この時期の体験活動は雨模様を心配しながらのことになります。あさひ保育園もこの日20日が、3度目の予定変更で、ようやく実行できたジャガイモ収穫でした。翌21日は、生活体験合宿(1泊2日)2班17名がジャガイモの収穫体験をしました。参加したのは、立岩小、鯰田小、庄内小、飯塚東小の4校からでした。収穫した場所は南の菜園で、収穫した総量は94.8㎏でした。21日の収穫は約100㎏といってよいでしょう。あさひ保育園のお持ち返りは28.5㎏でしたから、合わせて123.3㎏でした。 令和7年6月20日、あさひ保育園の5歳児がジャガイモの収穫体験にきました。この時期の体験活動は雨模様を心配しながらのことになります。あさひ保育園もこの日20日が、3度目の予定変更で、ようやく実行できたジャガイモ収穫でした。翌21日は、生活体験合宿(1泊2日)2班17名がジャガイモの収穫体験をしました。参加したのは、立岩小、鯰田小、庄内小、飯塚東小の4校からでした。収穫した場所は南の菜園で、収穫した総量は94.8㎏でした。21日の収穫は約100㎏といってよいでしょう。あさひ保育園のお持ち返りは28.5㎏でしたから、合わせて123.3㎏でした。 |
77 | |
| サツマイモのシーズンが始まりました (令和7年4月24日) 令和7年4月、今年もサツマイモの苗植えのシーズンがやってきました。植えたのは、22日(火)、今にも降り出しそうな曇り空の午後です。苗は、職員の矢野隆司さんが鹿児島県指宿市開聞十町のまつざわ農園から買ってきてくれた紅はるか(バイオ苗)300本です。矢野さんは私用で鹿児島まで出かけ、自家用のイモ苗と一緒に生活体験学校のイモ苗も買ってきてくれました。原和也さんの話では買ってきてすぐに植えるのではなく、苗に芽が出るのを確かめてから植えるのが良いとのこと。とはいえ、22日の夜には確実に雨が降ると言う雲行きですから、好機逃さず原さん、矢野さんが二人して300本を植えてしまいました。この苗から二番苗を採取して更に植え足します。5月には新たにバイオ苗700本を追加購入して、例年通り1200本余りを植えます。サツマイモのシーズンが始まりました。 |
76 | |
| 令和6年度、最後の生活塾 (令和7年3月23日) 令和7年3月23日(日)、生活塾21班が実施され、児童15名が参加しました。片島小学校2年生7名と3年生8名で、全員が片島小学校の児童でした。今回が令和6年度最後の生活塾でした。同じく最後になったのは石焼きイモでした。大ぶりのサツマイモ13個を焼いて児童に提供しました。大きいもので直径6~7㎝のイモもありました。11月に掘ったサツマイモを、3月末まで痛まないように保管するのは大変難しいのです。寒さに会わせるとすぐに痛んでしまいます。最後の石焼きイモは甘くておいしいイモでしたので、子どもに喜ばれました。農業体験として、ジャガイモ「メークイン」を2畝半植えました。このほか、小ぶりの大根を全量収穫しました。岩村先生の発案で大根を薄切りして生で子ども達に食べさせました。辛味もなくて食べられた、生の大根を初めて味わった子ども達でした。 |
75 | |
| シイタケのコマ打ち (令和7年2月23日) 令和7年2月23日(日)、生活塾18班の児童13名がシイタケのコマ打ちを体験しました。この日の13名は、上穂波小学校、片島小学校、菰田小学校のみなさんでした。コマ打ちは、シイタケのホダギ(原木)にシイタケ菌の入ったコマを木槌で打ち込む作業です。この日打ち込んだホダギは7本でした。1本のホダギ(原木)にはドリルで4~5列の孔を穿ちます。1列に6個か7個のコマを打ち込みますから1本のホダギに30個程度のコマを打ち込みます。わずか7本のコマ打ちですが、打ち込まれたコマの数は200個を超えます。生活体験学校のコマ打ちの凄いところは、ホダギ(原木)を購入するのではなく、自前で育てたクヌギを伐採して使うところです。ドングリから育苗、定植して15年から20年近く育てたクヌギを自分たちで伐採しているのですから、他所ではできないコマ打ちです。 |
74 | |
| 手作り味噌作り (令和7年2月22日) 令和7年2月22日(土)、キューピーみらいたまご財団の助成プログラム「食育キッズ講座」を実施しました。講座のテーマは、手作り味噌作りでした。参加者は大人5名、こども5名でした。食育キッズの活動内容は、野菜作りと収穫した野菜を使った調理実習です。年間全10回実施している講座で、令和2年(2020)から継続して助成を受けています。出来上がり3㎏の大豆を原料にした味噌作りです。大豆550g、麹1200gを準備しました。前の日から大豆を浸水させておいて、通常の蒸し方で3時間蒸しました。蒸した大豆をジップロックに入れつぶします。つぶした大豆をボウルに入れ、麹・塩を入れよくまぜます。保存容器に押し込み、唐辛子を1本入れ焼酎をしみこませたガーゼをかぶせて、冷暗所で寝かせるという作業をしました。講師の浅田暁子先生のリクエストで石焼きイモに麹を混ぜて石焼きイモ味噌を作りました。1年後、どんな味噌ができるのか今から楽しみです。 |
73 | |
| 秋ジャガと八朔の収穫 (令和6年12月23日) 令和6年12月22日(日),生活塾15班が実施されました。冬場のインフルエンザの影響もあって参加者は10名でした。庄内小学校、飯塚鎮西小学校、伊岐須小学校の3校からの参加者でした。この日の体験活動のメインは秋ジャガイモの収穫でした。10名がそれぞれ1株掘り、総量は約16㎏で、各自のお持ち帰りにしました。残りの3畝は生活体験学校の職員で掘りましたが、総量は約25㎏で、この日の総量は約41㎏になりました。この日の昼食は子どもが作った小さめのおにぎりとチャンポンでした。加えて、八朔のむき身が添えてありました。この八朔は、生活体験学校正門の北側に随分以前に移植された果樹で、毎年実をつけてはいましたが、これまで食材として子どもに提供されたことはありませんでした。厚い外皮を切り取って袋身の薄皮を剥いで1つだけがサラダに添えてありました。少し酸っぱい味がしましたが、十分な甘みがあって食べられる果肉になっていました。初物でした。 |
72 | |
| 自力で作る石焼きイモ (令和6年11月18日) 自園で石焼きイモを作るこども園があります。「自園で」と言うのは、場所のことではなくて自分たちの力でイモを焼くという「こども園」のことです。今年も、11月18日午前9時、職員2人が生活体験学校に軽トラックで乗り付けました。軽トラックを貸してくれたのは、園児のおじいちゃん(祖父)です。自分たちでイモ釜2基を積み込んで、釜以外に生活体験学校から借りたのは薪割り1丁と火ばさみ2本だけでした。JAの支援を受けて園児が栽培したサツマイモ6㎏を園庭で焼きました。参加した園児が70名、先生方が4名、保護者が7名でした。保護者会の会長さんを中心に、保護者の中には調理の専門家もいるという集団が支えています。今年で3年目になるという取り組みですが、この素晴らしい取り組みをしているのは潤野こども園です。 |
71 | |
| 石だらけの土で作った畑 (令和6年11月11日) 今年のサツマイモ栽培は昨年と違って南の菜園全面をあてました。昨年は全面北の菜園での栽培でしたから、そっくり入れ替えたわけです。想定外だったことは、南と北では土の硬さが違いました。南の菜園の土は園児が手で掘れるほど柔らかかったのですが、南の菜園はスコップやクワを使わなければ掘れない硬さでした。その原因をいろいろ詮索しましたが、決定的な要因は客土の差でした。客土とは既存の場所に新たな土を投入することです。 南の菜園は、生活棟や生活文化交流センターの建設の際、浄化槽埋設や基礎の床掘りで出た、その土を広げて、それだけで畑にしようとしたからでした。畑とは名ばかりで、子どもの頭ほどの石が出てきたり、工事に使ったバラスの残りがザクザク出てきたりという具合いです。いっぽう、北の菜園は最初の10年間は乗馬のための馬場として使っていましたので、毎年トラックに何台もの砂を入れ続けました。石だらけの畑と砂を補充しつづけた畑では、硬さに違いがあるのは当然でした。 |
70 | |
| イモ掘りの季節到来 (令和6年10月4日) 今年もイモ掘りの季節がやってきました。イモ掘りが始まれば、追いかけて石焼きイモも始まります。生活塾9班に参加した子どもが、試しに掘ったイモを食べたのは9月29日(日)でしたが、この日、イモ掘りを体験したわけではありません。初めての幼児のイモ掘り体験は、10月10日(木)、飯塚東保育園の園児21名でした。主催事業の児童のイモ掘り体験は、13日(日)、生活塾10班の子ども13名でした。両日ともにイモの実入りは適度で、サイズは焼きイモ向きの細長いタイプで満足のいくものでした。掘ったイモはすぐに焼くわけではありません。少なくとも1週間はおいて焼かなければ甘みが出ません。掘ったイモは土を落として太陽に当てて乾燥させます。最低でも1日おいて1個ずつ新聞紙に包んで段ボール箱に立てて収納します。焼く前にイモを洗って土を落とし、釜に入れて焼きます。10月、11月は、イモ掘りと石焼きイモの日程がびっしり詰まっています。 |
69 | |
| クリ拾いの季節 (令和6年10月4日) クリ拾いの季節は、サツマイモ掘りの前にやってきます。お盆を過ぎてサツマイモ掘りが始まる前です。 令和6年の初めてのクリ拾いは8月17日でした。東のクリ(大工小屋の裏)が70個ほど落ちていたのですが、強風のせいで落果したクリがほとんどで、青みがかっていて熟れたクリはわずか10個でした。8月27日には東のクリ130個を拾いました。8月22日は南のクリ畑の草を刈りました。草を刈っておかないと落ちたクリを探すのが難しくなります。南のクリは令和2年度と3年度にそれぞれ10本ずつ新規に植えた苗木です。南のクリの初収穫は9月19日で14個でした。9月24日に100個収穫(別に虫食いが10個)、9月26日に同じく100個収穫しました。合わせて200個ほど収穫しましたが、生活体験塾9班の子どもに茹でて持ち返らせました。ゆでたクリを包丁で半分に切ったものを持たせましたが、酷暑の影響か味もみかけも今一つでした。9月30日には4㎏を収穫しました。翌日、10月1日には更に3㎏を収穫し、更に4日に2㎏を収穫しました。合わせて9㎏を収穫しました。南のクリとしては最大の収穫量でした。冷蔵していますが、次回参加の子どもに食べさせたいと思っています。 |
68 | |
| 落葉囲いの残土を片づけた (令和6年8月8日) 令和6年8月3日(土)、九州大学社会教育主事講習の受講生17名が同講習の一環である「社会教育実践演習」のため生活体験学校にやってきました。演習内容は、「落ち葉囲いの残土処理」「シイタケ原木の移設」「施設見学・説明」でした。受講生の支援に筑豊教育事務所社会教育室から3名の社会教育主事が来てくれて総勢20名の規模になりました。「落ち葉囲い」と名付けたのは、野菜収穫の際に片づける茎、根、葉、土をまとめて放り込む囲いのことです。この囲いを作り始めたのが令和3(2021)年8月だから丸3年分の収穫残土が積まれていたのです。この土をスコップやエビジョウケを使ってリヤカーに積んで北の菜園に運ぶという作業でした。シイタケ原木の移設は、昨年冬にコマ打ちしたホダギを木積してあったものをシイタケ畑に移して立て掛ける作業でした。二手に分かれて作業を始めたのですが、どっと汗が噴き出して全員が汗だくになりました。僅かな作業でも大変なのに二つともに作業量は重たいものでした。昼過ぎまでかかった作業が終わった後には、「達成感を味わった」という参加者の声がいくつもありました。20人の大人がそろって大汗をかいた、その後の爽快感は格別でした。 |
67 | |
| 昼食に出た初物、縞マクワウリとブルーベリー (令和6年8月4日) 令和6年8月4日、生活塾6班の2・3年生12名が生活体験学校にやってきました。夏休みも半ばに近づきつつある酷暑続きの日曜日です。取り組んだ体験活動は、サツマイモのツル返しとナスの収穫でした。この日の昼食に生活体験学校で取れた初物が二つ提供されました。一つはマクワウリでした。マクワ瓜は、ウリ科キュウリ属のツル性の果実でメロンの変種とされています。この日のウリは縞マクワウリでしたが、インターネット情報にはタイガーメロンと紹介されていました。このウリの苗は平素から指導をお願いしている荻原史朗先生にいただいたものでした。前の日に3個ほど収穫して冷やしておいたものを薄く切って子どもたちに食べてもらいました。ほんのり甘みがあって美味しいウリでした。初物の他の一つはブルーベリーでした。作業棟の北隣の草地に15本植えてある幼木ですが、半数程度が実を結び始めています。植えて2~3年しか経っていませんので粒は小さいのですが、12名の子どもたちに分配することができました。 去年の8月下旬にはクリ拾いを始めました。夏の終わりには、クリの収穫が待たれる季節となりました。 |
66 | |
| ジャガイモ100㎏掘りました (令和6年6月14日) 令和6年6月11日、あさひ保育園(飯塚市川島)の5歳児24名、職員4名がジャガイモの収穫にやってきました。一畝分を掘りましたが、総量31㎏ありました。そのうち16㎏をお持ち帰りにしました。2日後の13日、庄内保育園(飯塚市綱分)の3歳児から5歳児までの39名、職員7名が同じようにジャガイモの収穫にやってきました。2畝分を掘りましたが、総量66㎏ありました。そのうち25㎏をお持ち帰りにしました。同時に、ご近所の高齢者施設「レイクヒルズ飯塚」の高齢者4名と職員1名が幼児の活動を見学にきました。見学の帰りに、ジャガイモ6㎏が同施設に贈呈されました。生活体験学校の菜園で育てているキュウリをもらった高齢者が喜んでいました。幼児の収穫体験と高齢者の見学体験、どちらも生気にあふれた6月の一日でした。 |
65 | |
| 2番苗90本植えました (令和6年6月8日) 令和6年6月8日、サツマイモの2番苗90本を植えました。植えたのは令和6年度第1回目の生活体験塾の17名、穂波東・飯塚東・椋本小学校の児童でした。先だって4月23日、300本の苗を植えておきました。その伸びたツルを切り取って植えましたが、その苗を2番苗と呼んでいます。南の菜園の、西側北寄りに8畝を2番苗用に空けておきました。8つの畝のうちの3畝に植えました。一畝にだいたい30本程度を植えていきますので、3畝で約90本ということです。残り5畝にも植えていきますから、全部植え終われば2番苗だけで約240本の計算になります。2番苗だから収穫時にイモが小さいなどということはありません。残り150本も6月中に植えてしまいます。 |
64 | |
| 通学合宿が始まりました (令和6年6月6日) 令和6年5月26日(日)から6月1日(土)まで6泊7日の通学合宿が行われました。  この合宿に参加したのは、庄内小学校の4年生から6年生までの希望者19名でした。約2㎞を歩いて登校する徒歩通学と日程が長いのが通学合宿の特徴です。期間が長いということは、子どもにすれば親離れの第一歩ですし、親の立場からすれば子離れの第一歩になります。1989(平成元)年に始めた通学合宿ですが、親離れ子離れのドラマはたくさん生まれて現在に至っています。今回も1名が自宅に帰ってしまいました。他にも2名がホームシックにかかって何度も夜中に帰ることになりましたが、それでも2日間だけは生活体験学校に泊まることができました。泊まれたから〇、泊まれなかったから×、というわけではありませんが、いずれやってくる親離れ子離れの心準備としては一週間程度の体験は必要だろうと思います。 この合宿に参加したのは、庄内小学校の4年生から6年生までの希望者19名でした。約2㎞を歩いて登校する徒歩通学と日程が長いのが通学合宿の特徴です。期間が長いということは、子どもにすれば親離れの第一歩ですし、親の立場からすれば子離れの第一歩になります。1989(平成元)年に始めた通学合宿ですが、親離れ子離れのドラマはたくさん生まれて現在に至っています。今回も1名が自宅に帰ってしまいました。他にも2名がホームシックにかかって何度も夜中に帰ることになりましたが、それでも2日間だけは生活体験学校に泊まることができました。泊まれたから〇、泊まれなかったから×、というわけではありませんが、いずれやってくる親離れ子離れの心準備としては一週間程度の体験は必要だろうと思います。 |
63 | |
| サツマイモの苗、千本植える (令和6年5月12日) 令和6年5月11日、サツマイモの苗700本のうち650本を南の菜園に植えました。残りの50本は5月14日に園児が植えます。今年の苗も鹿児島県の指宿から取り寄せました。5月11日に先立って4月23日に300本の苗を植えておきました。すでに活着していますが、この苗からは二番苗を切り取って使う予定で、そのため早目に植えたものです。二番苗は南の西北寄りに約200本を植える予定です。この200本だけはまだ植えていませんのでマルチを張ったままです。そこを終え終わると南の菜園は全面がサツマイモ畑になります。去年は植え終わった翌日から日照りが続いたので水やりに苦労しましたが、今年は翌日の5月12日に早速雨が降ってくれて、幸先の良いスタートが切れました。 |
62 | |
| ジャガイモの芽が出た (令和6年3月30日) 令和6年3月1日、ジャガイモを植えるため北の菜園B列西の端に畝5つを立てた。  翌2日、その5畝にそれぞれ種ジャガ20個を植えた。植えた後、畝ごとにマルチ(ビニール)をかけた。植え終わったところで、残った種ジャガ(メークイン)を、東のフェンス際に一畝植えて全て終わった。合わせて120個程度植えたことになる。それから、20日あまり経った3月26日、ジャガイモの芽が伸びてマルチを押しあげているのが分かるようになった。マルチを切り開いて芽を出してやる。3月29日、溝の土を平ぐわで跳ねあげてやると、風にあおられていたマルチが押さえ込まれて落ち着いた。あとは6月の中・下旬の収穫を待つことになる。 翌2日、その5畝にそれぞれ種ジャガ20個を植えた。植えた後、畝ごとにマルチ(ビニール)をかけた。植え終わったところで、残った種ジャガ(メークイン)を、東のフェンス際に一畝植えて全て終わった。合わせて120個程度植えたことになる。それから、20日あまり経った3月26日、ジャガイモの芽が伸びてマルチを押しあげているのが分かるようになった。マルチを切り開いて芽を出してやる。3月29日、溝の土を平ぐわで跳ねあげてやると、風にあおられていたマルチが押さえ込まれて落ち着いた。あとは6月の中・下旬の収穫を待つことになる。 |
61 | |
| サツマイモの成果2つ (令和6年3月3日) 令和5年度のサツマイモについて、これまで達成できなかった課題を2つ解決できました。一つはイモヅルの活用と、もう一つはサツマイモの長期保管です。これまで収穫の後に大量に残っていたイモヅルですが、今年は刈り取った後、完璧に乾燥させました。乾いたイモヅルをはみ切りで細断しました。これを餌としてヤギに与えたところ、嫌わずに食べてくれました。サツマイモの長期保管は今年初めて3月まで痛むことなく保管して石焼イモとして子どもに食べさせました。「これまでで一番美味しかった」と大変好評でした。寒さに弱いサツマイモを一個づつ新聞紙に包んで、縦に立ててダンボール箱に入れ、暖房の効果が期待できる事務室に置いたことで3月まで持たせることに成功しました。とろける甘さの石焼イモを期待して生活体験学校にくる子どもがいます。 |
60 | |
| ジャガイモの畝立て (令和6年3月2日) 令和6年2月23日(金)北の菜園B列西側にジャガイモの畝立てをしました。畝の数は5畝でした。数日前から雨が続いて土は濡れたままで、職員の河中さんに尋ねたら平ぐわを使って作業したとのこと。体がこわったと笑っておられました。その後も雨が降って土が乾く間もありませんでしたが、種ジャガは入荷しています。3月1日(金)、翌日には植え付けをしなくてはなりません。今度は管理機を使って再び畝立てをしました。ぬかるみの畑で管理機は自力だけでは進みません。管理機の前方にロープをかけて引っ張りながら2人がかりで畝を立てていきました。翌日2日(土)になると、晴れ間が見えて畑はようやく乾いてきました。2日(土)の午後、小学生10名が5つの畝にジャガイモを植え終わりました。ジャガイモの畝立ては大仕事でした。 |
59 | |
| シイタケのコマ打ち (令和6年2月13日) 令和6(2024)2月11日、生活塾20班が催され、2年生・3年生合わせて14名が参加しました。  参加者の学校別は、頴田小学校、穂波東小学校の2校でした。前回のホットニュース「玉切り」で書きました25本のホダギのうちの10本のホダギを使いました。コマ打ちは、ホダギにドリルで孔をあけてシイタケ菌の詰まった丸みがかった木片を打ち込みます。ホダギには4列の孔をあけますので、かなりの数のコマを打ちます。打ち込みには木槌を使います。力の入れ具合によって、コマは深く入ったり浅く入ったりします。浅く入ったままだとシイタケ菌の広がりを狭くしてしまう恐れがあります。力の入れ方の加減を習得する体験活動です。 参加者の学校別は、頴田小学校、穂波東小学校の2校でした。前回のホットニュース「玉切り」で書きました25本のホダギのうちの10本のホダギを使いました。コマ打ちは、ホダギにドリルで孔をあけてシイタケ菌の詰まった丸みがかった木片を打ち込みます。ホダギには4列の孔をあけますので、かなりの数のコマを打ちます。打ち込みには木槌を使います。力の入れ具合によって、コマは深く入ったり浅く入ったりします。浅く入ったままだとシイタケ菌の広がりを狭くしてしまう恐れがあります。力の入れ方の加減を習得する体験活動です。 |
58 | |
| シイタケ原木の玉切り (令和6年2月5日) 令和6(2024)2月4日、立川ブラインド工場敷地法面に植えたクヌギ4本を玉切りして25本のホダギにしました。  ホダギは中程度のものが直径12~15㎝で15本、小が直径8~12㎝で10本でした。玉切りとは冬に伐採したクヌギを1m程度のシイタケ原木に切ることをいいます。今年度の場合は、昨年12月26日に伐採しました。倒したクヌギ4本はその場にそのまま寝かせて、約1か月乾燥させて玉切りしました。シイタケを原木栽培するには玉切りした原木に穿孔し、コマ(シイタケ菌)を打ち込んで更に2年待たなければいけません。 ホダギは中程度のものが直径12~15㎝で15本、小が直径8~12㎝で10本でした。玉切りとは冬に伐採したクヌギを1m程度のシイタケ原木に切ることをいいます。今年度の場合は、昨年12月26日に伐採しました。倒したクヌギ4本はその場にそのまま寝かせて、約1か月乾燥させて玉切りしました。シイタケを原木栽培するには玉切りした原木に穿孔し、コマ(シイタケ菌)を打ち込んで更に2年待たなければいけません。 |
57 | |
| 訃報 (令和6年2月4日) 昨年(2023・令和5)10月30日、横山正幸先生(福岡教育大学名誉教授)が急逝されました。同年11月8日、三浦清一郎先生(月刊生涯学習通信「風の便り」編集長)が急逝されました。お二人ともに社会教育、生涯学習の理論的指導者として福岡県内はおろか全国的に影響を与え続けてこられた研究者でした。わが生活体験学校の運営に関しても度々貴重な助言と指導をいただきました。全く余人をもって代えがたい柱石を一度に二人も失いました。悔やんでも悔やみ切れない悲しみです。生前いただいた助言と指導を反芻しながら生活体験学校の運営に力を尽くしてまいります。 |
56 | |
| コガネムシ参上 (令和5年11月4日) 去年の生活体験学校のサツマイモにはオケラの食害の跡がみられました。きれいなサツマイモを期待して掘ったイモに、ケラにかじられた跡があると腹立たしいものです。今年は北の菜園の4分の1ほどにナスビなどを植えて、その減らした分、南の菜園の西側に400本弱のサツマイモを植えてみました。全体の本数としては大した増減はなかったのですが、去年は見なかったコガネムシの食害が出現しました。ケラに比べると傷跡が少し大きい。原因は自家生産している堆肥を餌にコガネムシの幼虫が増えたらしいのです。野菜作りの師匠荻原先生に相談したところ、椿油の絞り粕が有効とのこと。インターネットで調べてみたら確かに椿油粕の広告が出ていました。コガネムシとの戦いを考えているところです。 |
55 | |
| ニホンミツバチの採蜜 (令和5年11月3日) 11月3日(金)、河中さんと弟高志のコンビがニホンミツバチの巣箱3つから一箱づつ採蜜しました。巣箱は落ち葉囲い(北東)の脇と隣地西鉄運輸のフェンス際とクリ畑西端の3カ所でした。巣箱自体の総重量は3カ所合わせて29㎏、蜜量自体の重量は、推定ですが約21㎏でした。どの巣箱も天敵の攻撃を受けておらず巣房に美しい蜜が充満していました。これまでは、ダニかスムシかスヅメバチの攻撃を受けていて、無傷の巣箱から採蜜したのは 今回が初めてでした。これから巣房の細かな残り滓などを漉せば蜜量も少しは減りますが、 まずまずの成果といえるでしょう。 |
54 | |
| 九州女子短期大学の学外研修 (令和5年10月22日) 九州女子短期大学(北九州市、略称九女)には、「子ども健康学科」があります。希望すれば養護教諭と保育士の資格が取れます。その学科に「子ども健康学科特論」という科目があって、生活に関する体験活動の知識・技能を獲得し、仲間と協働する力を身につけることを目的として開講されています。今年初めての試みでしたが、3回に分けて講義と実習をおこないました。10月5日に九女で受講者全員に講義を行い、10月15日(日)と同22日(日)に学生を14名づつに分けて実習しました。実習内容は生活体験学校で大学生と小学校1年生が組んで、さつま芋収穫やおにぎり作りを協働して行いました。1年生も学生も喜んで体験活動に取り組みました。 |
53 | |
| 今年のクリは? (令和5年8月22日) 去年のクリの初物は8月20日だった。9月4日に400個拾ったのが最高だった。南側斜面に植えた新しいクリは、8月25日に100個拾ったのが最大だった。去年に比べると樹幹は太ったが、果たして実のつき具合がどうであろうか。 |
52 | |
| 生活体験学校の社会教育実践演習 (令和5年8月18日) 今日、ここに来て。一目見て、わ!!好きな所だ!と思いました。動物がいて、植物が育っていて、アスファルトの作業をしていたら子供達が、わーっとやってきた。なんて、命を楽しくする場所だろうと嬉しくなりました。作ること、食べること、生きていく力をみつめる数日間、そのひと時であっても、おいもをほって土を感じて、という時間を与えられる場作り、すばらしいです。こんな場所もっとあればいいな、長く続くといいなと心から思います。私達が作ったアスファルトの道がここで過ごす子供達の安全に少しでも役立てるといいなと思います。なんか・・また来たいんですけどと、思ってます。 |
51 | |
| セメンント流し、その2 (令和5年8月14日) セメンント流し㊾の続きです。別の参加者は次のように書いています。私は來る前は、とてもきつい作業が待っている、暑くてつらいことばかり考えていました。しかし、初めてみんなでコンクリートの舗装作業を行う過程で、分からないなりにも各パートに自然と分かれ、確認しながら懸命に取りかかり共動で行う作業は一体感があり、やりがいも出て、完成した時はとても嬉しかったです。左官の職人さんが行うパテの作業が初めてできて道路ができ、一生に一度のいい思い出にもなり、あわせて私の社会教育としての学びにもなりました。楽しかったです。 |
50 | |
| セメンント流し (令和5年8月6日) 令和5年8月5日(土)、生活体験学校で九州大学社会教育主事講習の社会教育実践演習が行われました。演習テーマは全体としては5本あって、その一つが生活体験学習で16名の受講生が参加しました。5つの会場の一つが生活体験学校でした。今年の演習テーマは劣化したアスファルトの表面にセメントを流して凹凸を直して平らにする作業でした。劣化したアスファルトは、混ぜてある砂利が表面に露出して、幼児が転倒でもすれば裂傷は免れないという危険な状態になっています。参加した受講生の一人は次のように書いています。「セメントで道路を舗装する」初めての経験でした。普段、当たり前のように舗装された路面を歩いたり車で走ったりしますが、その道も誰かが作っているものだと改めて考えさせられました。10数人で2時間程度取り組んで出来上がったのは数m。作業の大変さを身をもって知ることができました。 |
49 | |
| ジャガイモ掘り (令和5年6月24日) 令和5年6月24日(土)生活体験学校で食育キッズの活動がありました。今回の活動はジャガイモ掘りでした。食育キッズは、キューピーみらいたまご財団の助成を受けて、1年間活動しています。活動内容は季節ごとに様々ですが、今回の活動は荻原史朗先生に野菜の収穫について指導をお願いしました。感想を紹介します。三さわ千夏さんは、次のような感想を書きました。「ジャガイモが大きくてびっくりしました。」「頭が出たじゃがいもは、リラニンというのがついて緑色になったことがわかりました。」金子まなさんは、「ばれいしょは、あつまって土の中でできる。メークインは、広がってできるので、広―く掘る!」「じゃやがいもの実はたべない。」今まで知らなかったことを、たくさん学んだジャガイモ掘りでした。 |
48 | |
| ヤギの親子が、それぞれ出産 (令和5年6月6日) 今年、ヤギが双子を産んだことは既に書きました(44回目のホットニュース)。それは、2月8日のことです。このヤギは、NPOドングリが生活体験学校の指定管理者になった年にもらってきたヤギですから、8年もいることになります。このヤギが産んだ子どものヤギが初めて出産しました。4月28日のことです(46回目のホットニュース)。前回書いた2月の双子は2頭とも育ちませんでした。前回4月のホットニュースに、今回の双子が育つかどうか危ぶんでいると書きました。黒毛のメスは母乳を飲んで順調に育っていきましたが、茶色の毛がまじったオスは乳房に吸い付く前に母ヤギが動いて容易に母乳を飲ませません。以前、生活体験学校のヤギの飼養の指導をお願いした生山さんが様子を見にきてくれて、人口乳を飲ませないと育たたないと言い残して帰りました。5月1日、12時に100cc飲ませたのが最初で、この日4回340ccを飲ませました。2日には21時に160ccを甲斐希望さんが哺乳しました。5月いっぱい哺乳が続きました。今はどうやら草を食むようになりました。幸せなヤギです。 |
47 | |
| 再び双子のヤギが生まれたが、 (令和5年4月28日) 令和5年4月28日(金)の昼ごろ、2回目、双子のヤギが産まれました。2回目といっても産んだのは今年2月に産んだ母ヤギとは違います。母ヤギの子が産んだ、初産の双子です。一頭の毛色は真っ黒で、もう一頭は茶色がかった毛です。クロの方は自分から盛んに動いて乳房を求めますが、茶の方は足が弱いのか、あるいは足を痛めているのか、なかなか乳房にたどりつきません。そうこうしているうちに、親ヤギの方が動いてしまうので乳房は遠くなってしまいます。それでも何回かは乳房にたどりついたりしていますが、心もとない動きです。「ヤギは一産一子」と言われた獣医の犬丸先生の言葉が頭をよぎります。今、生活体験学校で飼っているヤギは白一色の2頭です。今日産まれた2頭は白一色ではありませんので、清野さんに借りていた黒毛のブチで小型のヤギが父親です。(こちらは既に清野さんにお返ししています)今回の双子は無事に成長してくれることを祈っています。向かいのウサギ小屋には、この3月産まれた白黒ブチの子ウサギ4羽が元気に走り回っています。 |
46 | |
| キンリョウヘンの花の香は流れても・・・(令和5年3月27日) 令和5年3月27日(月)午後、飯塚市内相田の村瀬先生のハウスにキンリョウヘンの鉢を借りに出かけました。インターネット情報では福岡県内のニホンミツバチの分蜂は既に始まっているらしいのだが、わが生活体験学校に分蜂の気配は見えません。去年の4月の初めには分蜂した蜂球を巣箱に早々と取り込んだものでしたが、今年は敷地内の巣箱で越冬した蜂群は一箱も見られません。その理由をあれこれ推測してみても、これぞという要因を思いつきません。ニホンミツバチの養蜂は実に分からないことだらけです。(この道のヴェテランからは、「当たり前」と言われるようなことなのですが)2年ぶりに産まれたウサギの子どもがかわいさをふりまいている生活体験学校の春です。 |
45 | |
双子のヤギが生まれたが、・・・(令和5年2月14日) 令和5年2月8日(水)、双子のヤギが生まれた。この日は生活体験学校の休館日で日直は正平高志さんだったが、産まれたのは高志さんの給餌の後だったらしく、職員が気づいたのは、10日(木)の朝だった。今回の双子は、毛が全身白と前身黒の二頭だった。10日の昼前になって白がうまく授乳してもらえていないらしく、衰弱気味である。獣医の犬丸先生の話では、ヤギは一産一子が多く二頭、時に三頭産まれても、二頭あるいは三頭ともに育つことは難しいらしい。前回の経験もあるからと正平高志さんが母ヤギから搾乳を試みてアルミ食器4分の1ぐらいを絞った。溜めた母乳を飲ませることはできたものの元気が出ない。原君が衣類を厚くしたり、哺乳瓶を活用するなど種々工夫はしてくれたが、11日まで持たなかった。いっぽうの黒毛のヤギも12日まで持たなかった。この日、生活塾21班の2・3年生が参加していたが、子ヤギの元気な姿を見せてやることはできなかった。 令和5年2月8日(水)、双子のヤギが生まれた。この日は生活体験学校の休館日で日直は正平高志さんだったが、産まれたのは高志さんの給餌の後だったらしく、職員が気づいたのは、10日(木)の朝だった。今回の双子は、毛が全身白と前身黒の二頭だった。10日の昼前になって白がうまく授乳してもらえていないらしく、衰弱気味である。獣医の犬丸先生の話では、ヤギは一産一子が多く二頭、時に三頭産まれても、二頭あるいは三頭ともに育つことは難しいらしい。前回の経験もあるからと正平高志さんが母ヤギから搾乳を試みてアルミ食器4分の1ぐらいを絞った。溜めた母乳を飲ませることはできたものの元気が出ない。原君が衣類を厚くしたり、哺乳瓶を活用するなど種々工夫はしてくれたが、11日まで持たなかった。いっぽうの黒毛のヤギも12日まで持たなかった。この日、生活塾21班の2・3年生が参加していたが、子ヤギの元気な姿を見せてやることはできなかった。 |
44 | |
| 石焼イモと石焼ジャガイモ (令和5年1月21日) 令和5年1月8日、生活塾19班が行われ、小学校2・3年生合計14名が参加しました。生活体験学校のサツマイモの収穫作業は11月末までに既に終わらせていました。去年の失敗は、畑に12月まで掘らずにおいたサツマイモが土中の寒さで痛んで、掘った後も更に痛みが進んでしまいました。今年こそはと、去年を思い出しながら11月中に終わらせました。その後、一ヶ月あまり過ぎました。それでも、冬は冬ですから、霜の害から守るためジャガイモの畝全体にブル―シートをかけて当日まで保護しました。今年のジャガイモは、デジマ、ニシユタカ、ながさきコガネ、アンデスレッドの4種類で、「ながさきコガネ」2畝、他の3種はそれぞれ一畝づつ植えました。当日は、早くに掘り上げて保管しておいたサツマイモを、石焼きにして食べられるほどに仕上げましたが、釜の中の火はまだ残っていて勢いがあります。この火を活かせとばかりに、たった今掘ったジャガイモ「デジマ」を子どもの人数分以上に焼きました。閉講式を終えて帰る子どもの手には、甘み十分の石焼イモと釜から取り出したばかりで熱々の石焼きジャガイモがありました。 |
43 | |
| ニホンミツバチの採蜜と天敵「スヅメバチ」 (令和5年1月11日) 年が明けて令和5年を迎え、「めでたくもあり、めでたくもなし」という元日を過ごしました。これから3月末に向けて年次報告書の執筆を進めます。書くという苦労はありますが、書きながら1年を振り返る反芻はいとも大事な営みです。書くべきテーマは山ほどありますし、どれも大事な取り組みです。ニホンミツバチ養蜂の成果は、令和4年9月17日、巣箱3つを空けて16㎏を採蜜しました。巣箱3つからそれぞれ一段づつ、合わせて3段を取り外したのですが、総重量は20㎏でした。蜜の重量だけで16㎏というのは最高の収穫でした。これを令和5年度の目標にしたいと思っています。この9月という月は、天敵であるスヅメバチの襲撃が最も激しい月です。捕獲器とバドミントンの古いラケットを駆使して捕殺した総数は462匹でした。年間の総捕獲数が667匹でしたから、9月ひと月で7割近くを捕殺したことになります。数こそ少ないものの4月初旬には早くもスヅメバチが来襲します。スヅメバチの攻撃目標は、スヅメバチそのものと蜂蜜です。まさに天敵です。ひとたび襲撃されれば人間の顔が変形するほどの猛毒をもつ難敵ですから、この戦いは半端なものではありません。令和5年度の闘いに勝利したいものです。 |
42 | |
| 男児の一言、「おもしろかったッ」 (令和4年11月17日) 今年は10月9日が最初のサツマイモの収穫日でした。今年のサツマイモ収穫を希望した園は10カ所です。どの園も始めと終わりには館長への挨拶をします。収穫活動も終わっていよいよ帰る時間が迫って、「さよなら」を言う直前、男の子が私の面前に近づくなり、「おもしろかったッ」と大きな声で言いました。私はその子の収穫の様子を見ていたわけではないので、何がどう面白かったのか、はかりかねて、ただうなずくだけでした。かねてから、多くの園で芋掘りをする理由は何だろうかと思っていました。長く幼稚園に勤めたOGに尋ねてみたこともありますが、やはりサツマイモでないといけないらしい。ほかの野菜ではサツマイモ掘りの代わりにはならないというのです。「そんなもんかなあ」という程度で今一つ得心がいきませんでした。その後、いくつかの園が芋掘りにやってきました。どの園にも引率の先生方にアンケートをお願いしています。その感想を書いてもらった中に次のような文章がありました。「芋掘りという貴重な体験をすることができ、子どもたちも掘っても掘ってもなかなか採ることができず、「どこまで続いているんだろう」という期待に胸を膨らましていました。 “〇〇したい”という子どもたちの思いが全面に出ており、非常に良い体験をすることができました。ありがとうございました。丁寧なお礼の文章でした。私などは、二人の息子の成長を妻と母に預けっぱなしにしてきた出来の悪い父親です。この文章を介して男児の一言の胸のうちを推察するほかありませんでした。 |
41 | |
| 保育者体験講座、「体験して初めて分かったこと」 (令和4年10月10日) 10月9日(日)の保育者体験講座は、保育者25名、子ども16名という参加人数でした。合わせて41名という参加人数は講座開始以来最高の人数で嬉しいことでした。体験のテーマは、芋掘りとクリ拾いとしました。クリ拾いは、9月いっぱいで収穫がほぼ終わっていましたので、付け加えてキャベツ苗の定植を体験してもらいました。アンケートの一部を紹介します。 ① 「船底植えと垂直植えでお芋の成長具合がかなり違っている点を知ることができた。」 ② 面白いと思ったこととして「細いイモと思いきや、長くてなかなか素手で掘れなかったけど、あきらめずに掘れたこと。」 ③ 「うちの子は虫がてんでダメで、畑に近づくのも虫がいるからと躊躇していましたが、最後は自分の手でいもをほりあげることができました。」 ④ 「どろだらけで、夢中でいもほりする姿が見られてよかった。」 ⑤ 「スコップを使わずに手で掘り、中々とれなかったことがすごく楽しかったです。」 ⑥ 面白いと思ったこととして「キャベツの苗植えの際、はじめて見た缶を利用したマルチの穴あけと畑に等間隔に穴をあける木の道具(イラスト入り)」 参加者アンケートを読んでいくうちに、親子で参加する保育者体験講座の意義や効果のようなものが、最初考えていたよりは大きいのではないかと思えてきました。  |
40 | |
クリが今年は豊作でした (令和4年9月29日) 9月はクリの収穫時期でした。9月2日に111個のクリを拾いました。4日が一番多くて400個拾いました。5日は160個、6日は230個、11日は130個拾いました。2日から27日までの間に1136個拾いました。このクリは主に大工小屋の裏の2本の木から収穫したものです。敷地南側の法面に10本づつ、2年がかりで20本植えた新しいクリの木があります。この木の収穫は9月25日、27日、29日の3日間で195個でした。大粒のクリで見るからに美味しそうな実でした。クリの収穫はサツマイモ収穫のように一斉に行うというわけにはいきません。落ちてきた実を集めるのですから、あらかじめ数を決めてというわけにもいきません。幸運にもクリ拾いができたのは9月11日(日)の生活塾11班の11名(2年生8名、3年生3名)と9月25日(日)の生活塾12班の10名(2年生7名、3年生3名)の子ども達でした。1回だけはクリご飯を作って出しましたが、大変喜ばれました。クリの収穫は何月何日と日にちが決められないこと、またあらかじめ収穫する数を決めてというわけにいかないのが難しいところです。ともあれ、今までなかったクリ拾いというプログラムが誕生したことだけは確かなことでした。 9月はクリの収穫時期でした。9月2日に111個のクリを拾いました。4日が一番多くて400個拾いました。5日は160個、6日は230個、11日は130個拾いました。2日から27日までの間に1136個拾いました。このクリは主に大工小屋の裏の2本の木から収穫したものです。敷地南側の法面に10本づつ、2年がかりで20本植えた新しいクリの木があります。この木の収穫は9月25日、27日、29日の3日間で195個でした。大粒のクリで見るからに美味しそうな実でした。クリの収穫はサツマイモ収穫のように一斉に行うというわけにはいきません。落ちてきた実を集めるのですから、あらかじめ数を決めてというわけにもいきません。幸運にもクリ拾いができたのは9月11日(日)の生活塾11班の11名(2年生8名、3年生3名)と9月25日(日)の生活塾12班の10名(2年生7名、3年生3名)の子ども達でした。1回だけはクリご飯を作って出しましたが、大変喜ばれました。クリの収穫は何月何日と日にちが決められないこと、またあらかじめ収穫する数を決めてというわけにいかないのが難しいところです。ともあれ、今までなかったクリ拾いというプログラムが誕生したことだけは確かなことでした。 |
39 | |
初めてのクリ拾い、やってみました(令和4年9月5日) 令和4年8月28日(日)、初めてのクリ拾いをやってみました。小学生5名が参加しました。子どもの参加は、コロナ感染の影響で1泊2日の予定を日帰りに変更するなど日程も人数も減少してしまいました。大人の参加者は、園長・所長の管理者2名でした。参加された菰田保育所の梅田利枝所長から次のような感想を寄せていただきました。 令和4年8月28日(日)、初めてのクリ拾いをやってみました。小学生5名が参加しました。子どもの参加は、コロナ感染の影響で1泊2日の予定を日帰りに変更するなど日程も人数も減少してしまいました。大人の参加者は、園長・所長の管理者2名でした。参加された菰田保育所の梅田利枝所長から次のような感想を寄せていただきました。今の子ども達は、イガに入った状態のクリを見る機会は少ないと思います。なので、木になっている状態から収穫できるのは、とても良い体験になるかと思います。ただ、イガで怪我をする恐れがあり、大人のように上手にイガから栗を取り出すのは難しいかと思います。だからといってイガから出した状態でするのは、体験にならない気がするので、少ない人数で、大人がしっかりついて収穫できるなら、子どもも体験できるのではと感じました。さつま芋の「基腐病」の話など、子ども達は、その食物ができるまでの大変な期間を知ることはできませんが、その手をかけないといけない大変な期間を知ることが大切だということも納得です。そのような事もしっかりと話をしてから、10月、11月にそちらに行きたいと思います。ありがとうございました。*「基腐病」は、「もとぐされびょう」。 |
38 | |
初めてのクリ拾いを計画します(令和4年9月3日) 古いクリの木が大工小屋の裏に2本あります。令和3年の記録では、2本の木から5回、約1000個のクリの実を拾いました。ところが、場所が狭くて今までクリを子どもに拾わせたことがありません。ちょうど2本のクリの木を隠すかのように薪をためておく小屋があります。この小屋を撤去すれば、幼児でもクリ拾いができるのですが、簡単には行きません。令和4年8月6日(土)、九州大学の社会教育主事講習受講生15名が社会教育実践演習のために生活体験学校にやってきました。加えて、筑豊教育事務所から主任社会教育主事以下4名が加勢にきてくれました。合計19名の成人の集団です。数を頼んで、薪小屋の屋根を持ち上げて、そのまま地面に倒して、トタンをはがし解体してもらいました。波トタンも鉄製のハサミで細断して、燃えるゴミ袋に収納して片付けてもらいました。その上、堆肥小屋の屋根掃除とシイタケのホダ木の天地替え、新しいホダ木の移設まで3つの大仕事を一度に片付けてもらいました。今年は、初めて幼児を招いてクリ拾いを計画しようと考えています。重たい仕事は、毎年九州大学の社会教育主事講習性の皆さんを当てにして待っている生活体験学校です。 古いクリの木が大工小屋の裏に2本あります。令和3年の記録では、2本の木から5回、約1000個のクリの実を拾いました。ところが、場所が狭くて今までクリを子どもに拾わせたことがありません。ちょうど2本のクリの木を隠すかのように薪をためておく小屋があります。この小屋を撤去すれば、幼児でもクリ拾いができるのですが、簡単には行きません。令和4年8月6日(土)、九州大学の社会教育主事講習受講生15名が社会教育実践演習のために生活体験学校にやってきました。加えて、筑豊教育事務所から主任社会教育主事以下4名が加勢にきてくれました。合計19名の成人の集団です。数を頼んで、薪小屋の屋根を持ち上げて、そのまま地面に倒して、トタンをはがし解体してもらいました。波トタンも鉄製のハサミで細断して、燃えるゴミ袋に収納して片付けてもらいました。その上、堆肥小屋の屋根掃除とシイタケのホダ木の天地替え、新しいホダ木の移設まで3つの大仕事を一度に片付けてもらいました。今年は、初めて幼児を招いてクリ拾いを計画しようと考えています。重たい仕事は、毎年九州大学の社会教育主事講習性の皆さんを当てにして待っている生活体験学校です。 |
37 | |
堆肥の発酵温度、ただ今、51℃です (令和4年7月20日)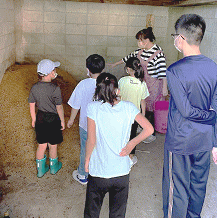 堆肥を作って畑に入れて、野菜作りに役立てる取り組みは1988(昭和63年)の生活体験学校開設以来の活動です。そもそもの始まりは、大型動物(馬)中型動物(羊)の飼養体験の一環として取り組んだ活動でした。現在はヤギ3頭、ウサギ4羽というささやかな動物飼養をしています。それでも、糞尿の始末はしないわけにはいきません。小屋の敷料はモミガラを使っています。糞尿にまみれたモミガラと合宿生活で出る生ごみを堆肥小屋に運んで発酵させます。令和4年7月9日、堆肥の発酵温度は51℃でした。盛んな発酵です。7月2日、生活体験合宿第1班、13名の小学生が体験活動で堆肥を畑に入れました。南の畑11m×8mの広さに入れました。作業量が多くて大変でした。今は堆肥小屋にモミガラを1.5mほどの高さに積み上げて発酵させています。発酵させる決め手は、家庭で廃棄される煮油を集めて堆肥の山に振りかけます。煮油にまみれた生ごみは盛んに発酵します。冬だと湯気が立つほどです。7月5日、持ち込まれた煮油を入れたペットボトルの空の容器をまとめて、燃えるゴミ袋2つに入れて廃棄しました。開設以来、一度も生ごみをゴミ収集車に出したことがない生活体験学校の取り組みです。 堆肥を作って畑に入れて、野菜作りに役立てる取り組みは1988(昭和63年)の生活体験学校開設以来の活動です。そもそもの始まりは、大型動物(馬)中型動物(羊)の飼養体験の一環として取り組んだ活動でした。現在はヤギ3頭、ウサギ4羽というささやかな動物飼養をしています。それでも、糞尿の始末はしないわけにはいきません。小屋の敷料はモミガラを使っています。糞尿にまみれたモミガラと合宿生活で出る生ごみを堆肥小屋に運んで発酵させます。令和4年7月9日、堆肥の発酵温度は51℃でした。盛んな発酵です。7月2日、生活体験合宿第1班、13名の小学生が体験活動で堆肥を畑に入れました。南の畑11m×8mの広さに入れました。作業量が多くて大変でした。今は堆肥小屋にモミガラを1.5mほどの高さに積み上げて発酵させています。発酵させる決め手は、家庭で廃棄される煮油を集めて堆肥の山に振りかけます。煮油にまみれた生ごみは盛んに発酵します。冬だと湯気が立つほどです。7月5日、持ち込まれた煮油を入れたペットボトルの空の容器をまとめて、燃えるゴミ袋2つに入れて廃棄しました。開設以来、一度も生ごみをゴミ収集車に出したことがない生活体験学校の取り組みです。 |
36 | |
2年ぶりの合宿再開(1泊)(令和4年7月5日)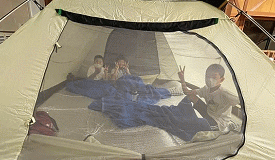 令和4(2022)年7月2~3日、生活体験合宿第1班が実施されました。参加したのは4・5年生が各6人、6年生が1人、計13人で、男子は7人、女子は6人でした。コロナ感染防止のために合宿を止めて2年以上の期間が過ぎ、この間、全て日帰りの体験活動にしました。その日帰り体験活動も感染者発生で直前に中止したことが何度もありました。生活体験学校の風呂は薪で沸かしますが、4日前に試しに風呂釜を焚いてみました。なにしろ2年以上も沸かしていない風呂釜ですから。今回から6回までは敷地内にテントを張って寝るテント泊としました。テント泊は思ったより多くの希望者がありました。あいにく台風4号が、今夜沖縄に最接近するという予報が出ていますので、風が強くなれば舎営に変更するかもしれません。日中の農業体験はサツマイモのツル返しをしました。ツルばかり伸びて肝心のイモが小さかったというのでは芋掘りになりません。伸びた先で根を張ろうとするツルを引き上げて、小さなイモを作らせない手入れです。いわゆる「ツルぼけ」を防ぎます。 令和4(2022)年7月2~3日、生活体験合宿第1班が実施されました。参加したのは4・5年生が各6人、6年生が1人、計13人で、男子は7人、女子は6人でした。コロナ感染防止のために合宿を止めて2年以上の期間が過ぎ、この間、全て日帰りの体験活動にしました。その日帰り体験活動も感染者発生で直前に中止したことが何度もありました。生活体験学校の風呂は薪で沸かしますが、4日前に試しに風呂釜を焚いてみました。なにしろ2年以上も沸かしていない風呂釜ですから。今回から6回までは敷地内にテントを張って寝るテント泊としました。テント泊は思ったより多くの希望者がありました。あいにく台風4号が、今夜沖縄に最接近するという予報が出ていますので、風が強くなれば舎営に変更するかもしれません。日中の農業体験はサツマイモのツル返しをしました。ツルばかり伸びて肝心のイモが小さかったというのでは芋掘りになりません。伸びた先で根を張ろうとするツルを引き上げて、小さなイモを作らせない手入れです。いわゆる「ツルぼけ」を防ぎます。 |
35 | |
| 高値を呼んだタマネギ (令和4年6月23日) 今年のタマネギは高値を呼んで、店頭で値札を見ては何度も驚きました。苗を植え付ける時期には予想もしなかったことです。生活体験学校ではタマネギ苗を2回に分けて植えました。1回目は11月28日、純真短期大学食物栄養学科の学生が食育キャンプにやってきた時に800本植えてもらいました。2回目は、年が明けて1月6日に800本植えました。合計1600本植えました。苗は種をトレーに植えて生活体験学校で育てたものです。2回目の1月6日には、飯塚東保育園に280本、らいむ保育園に200本の苗を運んで植えました。収穫期を迎えた5月29日、タマネギを掘って、翌日、段ボールに詰め純真短期大学あてに送りました。飯塚東保育園でも、らいむ保育園でも苗を植えた時には予想もしなかった高値のタマネギ掘りに、園児も職員も喜びに沸きました。 |
34 | |
| イモ畑の草取りを管理機でやりました(令和4年5月27日) 5月1日に鹿児島仕込みのサツマイモ苗1000本を植えたことは前に書きました。植えてから26日目の今日、初めて管理機を使ってイモ畑の草刈りをしました。管理機という機械は畝立てをする際に威力を発揮します。畑の溝を走りながら両方に、あるいは片方に土をはねあげて畝を形作っていきます。鍬で畝を立てる作業の何倍もの仕事をこなします。今年のサツマイモの畑は、2列ごとに今までの2倍の広さの溝を掘ってあります。幼児が2列で歩けるほどの幅です。畝の長さをそろえ、溝の幅を十分に広げて、初めて管理機を入れて草刈りが可能になったのです。北の菜園全部の草刈りを職員の河中利通さんが一人でこなしました。私は見ていただけでしたが、重たい管理機を縦横に動かして草刈りをする河中さんの姿に感動さえ覚えたことでした。 |
33 | |
| 劣化したアスファルトに生コンを打ちました(令和4年5月6日) 動物棟の前から窯屋(飯盒炊飯の場所)前までの間の通路が、雨風にさらされてアスファルトに混ぜてあった砕石がむき出しになっていました。このアスファルトは施工してから約30年は経過しています。よちよち歩きの幼児が転倒すれば頭にひどい傷がつく恐れがあります。アスファルトに混ぜてあった砕石の尖った角を丸くしておく必要があります。どうしたものかと大分思案しましたが、名案は浮かばず結局多めにセメントを混ぜて表面を覆うことにしました。5月3日に購入した左官用砂13袋では足りずに、5日の作業当日、20袋(20㎏)を買いに行って、全部使いました。幅3m、長さ22mの通路にコンクリートを打ち終えました。備品として小型のコンクリートミキサーがありましたので混ぜる作業では助かりましたが、それでも随分重たい作業でした。果たして、これで工事の目的を達成できるかどうか、しばらく様子を見ることにします。 |
32 | |
サツマイモの畑が、去年とは違います(令和4年5月11日) 今年もサツマイモの苗を植えるシーズンがきました。今年のイモ畑は例年とは違います。5月1日(日)に北の菜園全面にサツマイモの苗1000本を植え付けます。二番苗を含めて全部で1600本を植える予定ですが、その半分は保育園、幼稚園、こども園の幼児の体験活動に提供します。4月30日に鹿児島県開聞町からバイオ苗が届くように手配してあります。畑には、既にマルチを張り終えて、立てる園名札の準備も終わりました。畝と畝の間の溝は、2本に1本の割合で2倍に広げました。そのため、全区画とも畝2本を減らす結果になりました。減らした分だけ、収穫量は減りますが、園児の活動の自由は増大します。さらに、畑の全面に給水できる給水管を埋設しました。職員には大汗をかかせた大変な仕事でした。給水管埋設は、4月22日に河中、祝原、谷、高志の4人が行いました。16mmパイプ15本(1本4m)を用意して、56mを埋め込みました。経費は@537円×15本=8055円。蛇口(Y80J)が4個で@1560×4=6240円でした。資材費用の総額は、17,694円でした。ホームセンターなどで買えばもっと高い値段になっていたでしょう。これで、畑の全面に長いホースを曳きずり回して給水をする、そんな例年のような苦労は、しなくても済むようになりました。 今年もサツマイモの苗を植えるシーズンがきました。今年のイモ畑は例年とは違います。5月1日(日)に北の菜園全面にサツマイモの苗1000本を植え付けます。二番苗を含めて全部で1600本を植える予定ですが、その半分は保育園、幼稚園、こども園の幼児の体験活動に提供します。4月30日に鹿児島県開聞町からバイオ苗が届くように手配してあります。畑には、既にマルチを張り終えて、立てる園名札の準備も終わりました。畝と畝の間の溝は、2本に1本の割合で2倍に広げました。そのため、全区画とも畝2本を減らす結果になりました。減らした分だけ、収穫量は減りますが、園児の活動の自由は増大します。さらに、畑の全面に給水できる給水管を埋設しました。職員には大汗をかかせた大変な仕事でした。給水管埋設は、4月22日に河中、祝原、谷、高志の4人が行いました。16mmパイプ15本(1本4m)を用意して、56mを埋め込みました。経費は@537円×15本=8055円。蛇口(Y80J)が4個で@1560×4=6240円でした。資材費用の総額は、17,694円でした。ホームセンターなどで買えばもっと高い値段になっていたでしょう。これで、畑の全面に長いホースを曳きずり回して給水をする、そんな例年のような苦労は、しなくても済むようになりました。 |
31 | |
ニホンミツバチの分蜂が始まりました (令和4年4月7日) 令和4年4月6日(水)、巣箱2つにニホンミツバチが入りました。この日は週1回の休館日で出勤の必要はなかったのですが、ミツバチが動いているのではないかという期待もあって生活体験学校に来てみました。来てみると、弟の高志と河中さんの姿がありました。案の定、河中さんの話では桜の巣箱と北の菜園の東法面の巣箱にニホンミツバチが入っているのを確認したというのです。東の巣箱ではニホンミツバチが盛んに花粉を運んでいる様子で、どうやら巣箱に入ったのは昨日今日ではなさそうだということになりました。だとすれば、前の週の火曜日、3月29日(火)、堆肥小屋の巣箱で分蜂を疑われるような蜂球が見られたものの再び巣箱に戻ったらしいという話がありましたが、実はこの時既に東の巣箱に移り住んだのではないかという推測に落ち着きました。もう一つの桜の巣箱は、同じ29日(火)にキンリョウヘンの鉢を巣門に据えた時からニホンミツバチが飛び交っていたので、その日か翌日には巣箱に入っていたのだろうという推測になりました。キンリョウヘンの鉢を置いて一週間そこそこで女王バチが入ってくれたという幸先の良いスタートです。 令和4年4月6日(水)、巣箱2つにニホンミツバチが入りました。この日は週1回の休館日で出勤の必要はなかったのですが、ミツバチが動いているのではないかという期待もあって生活体験学校に来てみました。来てみると、弟の高志と河中さんの姿がありました。案の定、河中さんの話では桜の巣箱と北の菜園の東法面の巣箱にニホンミツバチが入っているのを確認したというのです。東の巣箱ではニホンミツバチが盛んに花粉を運んでいる様子で、どうやら巣箱に入ったのは昨日今日ではなさそうだということになりました。だとすれば、前の週の火曜日、3月29日(火)、堆肥小屋の巣箱で分蜂を疑われるような蜂球が見られたものの再び巣箱に戻ったらしいという話がありましたが、実はこの時既に東の巣箱に移り住んだのではないかという推測に落ち着きました。もう一つの桜の巣箱は、同じ29日(火)にキンリョウヘンの鉢を巣門に据えた時からニホンミツバチが飛び交っていたので、その日か翌日には巣箱に入っていたのだろうという推測になりました。キンリョウヘンの鉢を置いて一週間そこそこで女王バチが入ってくれたという幸先の良いスタートです。 |
30 | |
園児たちがシイタケのコマ打ちに挑戦 (令和4年3月22日) 令和4年3月18日、飯塚らいむ保育園の園児たち27名がシイタケのコマ打ちをしました。この事業は、福岡県森林づくり活動公募事業に応募し、助成金を得て実施したものです。あいにくの雨でしたが、園児たちは貸切バスに乗って元気いっぱいで生活体験学校に来ました。2班に分かれて活動しました。メインはホダギの穿孔した穴にシイタケのコマを埋め込み、木づちで打ち込む作業でした。大屋根の下でシイタケが生えたホダギを見学して、コマ打ちした後のシイタケ栽培のイメージをふくらませました。その後は、干しシイタケを擬人化した物語の絵本の読み聞かせを楽しみました。園児たちは生活体験学校で取り組んでいるクヌギの育苗や成木の伐採の話を聞いて、クヌギの木に対する関心を少しは抱いたようでした。 令和4年3月18日、飯塚らいむ保育園の園児たち27名がシイタケのコマ打ちをしました。この事業は、福岡県森林づくり活動公募事業に応募し、助成金を得て実施したものです。あいにくの雨でしたが、園児たちは貸切バスに乗って元気いっぱいで生活体験学校に来ました。2班に分かれて活動しました。メインはホダギの穿孔した穴にシイタケのコマを埋め込み、木づちで打ち込む作業でした。大屋根の下でシイタケが生えたホダギを見学して、コマ打ちした後のシイタケ栽培のイメージをふくらませました。その後は、干しシイタケを擬人化した物語の絵本の読み聞かせを楽しみました。園児たちは生活体験学校で取り組んでいるクヌギの育苗や成木の伐採の話を聞いて、クヌギの木に対する関心を少しは抱いたようでした。 |
29 | |
古いテントを処分した (令和4年3月22日)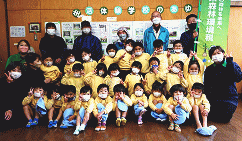 長い年月放置されてきた物を片づける作業は労力がいるものです。その典型的な物が紙でした。もう一つ片づけられずに、そのままになっていたのが野営のテントです。30年以上前の物もあるのですから、このうえなく古いのです。3月1日(火)、雨時々曇り、赤扉の倉庫内に積みあげられていたテントを、職員が二人がかりで燃えるゴミ袋に詰め込んで、ゴミ燃料化センターに持ち込みました。しかし、そのままでは受け取ってもらえませんでした。3月2日、持って帰ったテントを、軽トラックから新屋根の地面に降ろしました。3月5日(土)、詰め込んだテントをゴミ袋から、また引きずり出して一カ所に集めました。3月7日(月)曇り、風が冷たい。河中さんがテント付属のヒモを使って縛りあげました。数えたら31個ありました。さて、取りかかってから7日経ちましたが、この先どうやって処分するかが問題です。 長い年月放置されてきた物を片づける作業は労力がいるものです。その典型的な物が紙でした。もう一つ片づけられずに、そのままになっていたのが野営のテントです。30年以上前の物もあるのですから、このうえなく古いのです。3月1日(火)、雨時々曇り、赤扉の倉庫内に積みあげられていたテントを、職員が二人がかりで燃えるゴミ袋に詰め込んで、ゴミ燃料化センターに持ち込みました。しかし、そのままでは受け取ってもらえませんでした。3月2日、持って帰ったテントを、軽トラックから新屋根の地面に降ろしました。3月5日(土)、詰め込んだテントをゴミ袋から、また引きずり出して一カ所に集めました。3月7日(月)曇り、風が冷たい。河中さんがテント付属のヒモを使って縛りあげました。数えたら31個ありました。さて、取りかかってから7日経ちましたが、この先どうやって処分するかが問題です。 |
28 | |
| 20~30年前の文書を処分しました (令和4年3月7日) 生活文化交流センターの2階(ちょうど事務室の上にあたる所)には、生活体験学校開設以来の古い文書が山ほどあります。2月19日(土)は雨。2階から古い文書18ケース分を1階に降ろしました。1つのケースだけでも、一人では抱えきれないほどの重さです。ケースの前と後ろに紐をくくり付けて鉄製の階段を滑らせながら二人がかりで曳いたり押したりしながら降ろしました。降ろした文書の仕分けも大変でした。パンチファイルの金具は取り外して、燃えないゴミとして分けました。2月20日(日)曇り、寒気が厳しい一日でした。昨日の続きで古い文書を2階から降ろして分別しました。午前中いっぱいかかりました。2月21日 古い文書の片づけは終わりませんでした。2月24日(木)、古い文書を燃えるゴミ袋に追加して入れ込みました。嘉麻市岩崎のゴミ燃料化センターに搬入して処分しました。燃えるゴミ袋の大型で28個ありました。ゴミ燃料化センターの場所が分からず、以前、一度来たことはあったのですが随分前のことで、祝原政弘さんと正平辰男の二人はセンターを探し回わりました。11:30頃に終わりました。取りかかってから6日目に終わった作業でしたが、作業としてはかなり骨の折れる仕事でした。 |
27 | |
ニホンミツバチの巣箱を洞(うろ)に据える (令和4年2月26日)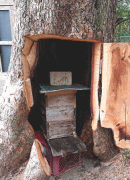 1月29日(土)たい肥小屋のそばのクスノキの洞(うろ)に巣箱を据える作業をしました。生活体験学校のクスノキは長い間枝降ろしをしていません。枝は伸びて畑に日陰を作り、根は畑に向かって伸びてきます。くだんのクスノキは上部を切り落とされて周りは1mを超える胴体だけになっています。そのまま切り倒してしまおうという見立てもありましたが、根元の空洞は人一人入れる広さがあります。職員の河中さんと高志さんの提案で洞(うろ)の入り口を切り開いて巣箱を据えることにしました。実際に巣箱を据えてみると、なかなか具合が良さそうです。ニホンミツバチにとって本当に具合が良いかどうかは、3月、4月になって分蜂が始まってみれば分かります。具合が良ければ入ってくれるし、悪ければ入ってもらえません。人間とハチの思いは同じではありません。果たしてうまくいくでしょうか、どうでしょうか? 1月29日(土)たい肥小屋のそばのクスノキの洞(うろ)に巣箱を据える作業をしました。生活体験学校のクスノキは長い間枝降ろしをしていません。枝は伸びて畑に日陰を作り、根は畑に向かって伸びてきます。くだんのクスノキは上部を切り落とされて周りは1mを超える胴体だけになっています。そのまま切り倒してしまおうという見立てもありましたが、根元の空洞は人一人入れる広さがあります。職員の河中さんと高志さんの提案で洞(うろ)の入り口を切り開いて巣箱を据えることにしました。実際に巣箱を据えてみると、なかなか具合が良さそうです。ニホンミツバチにとって本当に具合が良いかどうかは、3月、4月になって分蜂が始まってみれば分かります。具合が良ければ入ってくれるし、悪ければ入ってもらえません。人間とハチの思いは同じではありません。果たしてうまくいくでしょうか、どうでしょうか? |
26 | |
サツマイモの保管は難しい(令和4年1月25日) 1月15日(土)、純真短期大学の学生による最後の食育キャンプが行われました。学生2名がイモ焼き当番になって、石焼き芋を作りました。学生に提供したイモは小ぶりのものでしたが、味の方は好評でした。ところが、職員に提供した分、こちらは傷んでいて食べられないイモがありました。サツマイモが腐る原因の一つは低温障害で、温度が5℃以下になると傷むと言われています。1月20日(木)、職員4名が残っているイモ全部を点検して収納しなおしました。刷毛を使ってイモの土を払い落とし、一個ずつ新聞紙で包みます。そのまま、段ボール箱(サイズ80)に入れました。それを事務室の給湯室のキャビネットに収納しました。事務室の給湯室なら、5℃以下に冷え込むことはないだろうという見立てです。収穫時期も保存に影響するらしくて、遅くとも12月上旬には収穫を終えることが必要です。万事人間の都合ばかりを優先すると、まずいことが起こるという例でした。 1月15日(土)、純真短期大学の学生による最後の食育キャンプが行われました。学生2名がイモ焼き当番になって、石焼き芋を作りました。学生に提供したイモは小ぶりのものでしたが、味の方は好評でした。ところが、職員に提供した分、こちらは傷んでいて食べられないイモがありました。サツマイモが腐る原因の一つは低温障害で、温度が5℃以下になると傷むと言われています。1月20日(木)、職員4名が残っているイモ全部を点検して収納しなおしました。刷毛を使ってイモの土を払い落とし、一個ずつ新聞紙で包みます。そのまま、段ボール箱(サイズ80)に入れました。それを事務室の給湯室のキャビネットに収納しました。事務室の給湯室なら、5℃以下に冷え込むことはないだろうという見立てです。収穫時期も保存に影響するらしくて、遅くとも12月上旬には収穫を終えることが必要です。万事人間の都合ばかりを優先すると、まずいことが起こるという例でした。 |
25 | |
玉ねぎ苗の植えつけ(令和4年1月7日) 最初に玉ねぎ苗を植えたのは、昨年11月28日(日)、純真短期大学の食育キャンプの体験活動でした。この日は、純真の男子学生7名だけを一つに集めてあり、400本以上を植えました。苗の残りを次の日曜日12月5日の生活塾20班の児童が植えて、全部で800本の苗をキウイの畑に植えました。1月6日(木)、3カ所でタマネギ苗を植えました。南の菜園に2畝で800本植えて、飯塚東保育園の菜園に280本、飯塚らいむ保育園の菜園に200本植えました。6日だけで約1300本植えたことになります。生活体験学校に植えたタマネギの合計が1600本、2つの保育園に約500本、合わせて約2100本を植えたことでした。 最初に玉ねぎ苗を植えたのは、昨年11月28日(日)、純真短期大学の食育キャンプの体験活動でした。この日は、純真の男子学生7名だけを一つに集めてあり、400本以上を植えました。苗の残りを次の日曜日12月5日の生活塾20班の児童が植えて、全部で800本の苗をキウイの畑に植えました。1月6日(木)、3カ所でタマネギ苗を植えました。南の菜園に2畝で800本植えて、飯塚東保育園の菜園に280本、飯塚らいむ保育園の菜園に200本植えました。6日だけで約1300本植えたことになります。生活体験学校に植えたタマネギの合計が1600本、2つの保育園に約500本、合わせて約2100本を植えたことでした。 |
24 | |
| ナメタケを収穫しました(令和3年12月28日) 12月7日(火)、河中さんがナメタケを収穫して交流センターに持ってきた。少し大き目のボールにいっぱいの量で、形もそろっていて上物である。味噌汁に入れたら美味しいだろうと職員の話題になった。収穫した場所は、シイタケ畑の北の端、堆肥小屋との間である。日誌を繰ってみたら、令和2年3月1日と2日に記事があった。1日は、津山さんと正平高志の2人勤務、ナメタケのコマ打ち、シイタケの続きに25本埋設とある。2日は原、谷、河中、瀧石の4人勤務。ナメタケのコマ打ちの改善、ホダギを起こして不織布を張ってホダギを乗せ換えるとあった。ナメタケは桜の木に菌を打つ。前回のコマ打ちでは土にそのまま埋め込んだ桜木にコマ打ちをしたために、ナメタケが土にまみれて収穫しづらかった。そこで、野菜作りに使う不織布を地面に敷き込んで桜木を乗せ、コマ打ちをしたというのである。その効果があってナメタケが土にまみれず、きれいに収穫できた次第である。季節は冬である。 |
23 | |
| 落ち葉集めとタマネギ苗の定植(令和3年12月14日) 11月28日(日)、純真短期大学の学生による食育キャンプが行われました。この日、学生7名が鳥羽公園にクヌギの落ち葉拾いに行きました。落葉は幼児の落ち葉プールの遊びに使うためのもので、枝などを取り除いて「ふご」に集めました。幼児が落ち葉を放り投げて遊ぶ時に枝などが顔や目に当たるのを防ぐためです。最後は大きなコンテナバッグに詰め込みました。幼児が狂喜して喜ぶ落ち葉プールですが、事前の落ち葉集めは欠かせない作業です。午後は、タマネギ苗800本を用意して500本余りを定植しました。来年5月にはタマネギを収穫します。 |
22 | |
| イモ畑の圃場整理を始めました(令和3年11月5日) 一般には圃場整備(ほじょうせいび)と呼ばれていますが、生活体験学校の場合はささやかな事業ですから圃場整理としておきます。(通常、圃場整備では耕地区画の整備や農道の整備などが実施されます。)生活体験学校のイモ畑には、南北に1本、東西に3本の通路を設けています。通路で区切られているのは8区画ですが、区画ごとに畝の長さが違っていて、いちいち数えなければイモの本数が把握できません。畝の長さを約10mに揃えます。畝の数も幼児が動き易いように減らします。そのためには土を動かさなければいけません。土を運ぶ作業は力を要する仕事です。職員の汗がたくさん流れ出ます。 |
21 | |
石焼きイモの釜を積んで走る軽トラック(令和3年11月2日) 11月2日、あさひ保育園での石焼きイモ作りが今年最初の出前です。石焼きイモは、生活体験学校で焼く場合とイモ釜を園まで運んで園庭で焼く場合の二通りあります。送迎バスを持っていない園は、石焼きイモの出前を頼むことになります。生活体験学校のイモ釜はドラム缶を改造して作った手作りです。ドラム缶は使用済みのものは安く手に入りますが、イモそのものを入れる部分には油の臭いが残っているので使えません。イモを入れる部分には新品のドラム缶を使います。新品は値段が張ります。ドラム缶はサンダーで切って焚き口を作ったり、穴を空けて煙突を取り付けたりとさまざまな加工をします。ドラム缶に短い煙突のついた石焼きイモ釜を3台積んで走る軽トラックを見かけたら、生活体験学校の石焼きイモの出前事業だなと思ってください。 11月2日、あさひ保育園での石焼きイモ作りが今年最初の出前です。石焼きイモは、生活体験学校で焼く場合とイモ釜を園まで運んで園庭で焼く場合の二通りあります。送迎バスを持っていない園は、石焼きイモの出前を頼むことになります。生活体験学校のイモ釜はドラム缶を改造して作った手作りです。ドラム缶は使用済みのものは安く手に入りますが、イモそのものを入れる部分には油の臭いが残っているので使えません。イモを入れる部分には新品のドラム缶を使います。新品は値段が張ります。ドラム缶はサンダーで切って焚き口を作ったり、穴を空けて煙突を取り付けたりとさまざまな加工をします。ドラム缶に短い煙突のついた石焼きイモ釜を3台積んで走る軽トラックを見かけたら、生活体験学校の石焼きイモの出前事業だなと思ってください。 |
20 | |
少なかった参加者、多かったプログラム~保育者体験講座(令和3年10月25日)  本年度2回目の保育者体験講座が10月10日(日)に行われました。この日は、園の運動会の影響があって予定した参加者も少なかったのですが、直前の欠席者が出たりして結局保育士3名、児童1名という少ない参加者になりました。研究者の方は3名そろってご参加いただきました。参加者こそ少なかったのですが、体験活動のメニュ-は盛たくさんでした。収穫体験はサツマイモ掘りに加えて里芋も収穫しました。里芋は子イモを外してバケツに入れ水を加えてイモ洗い棒を使って皮をむく体験をしました。サツマイモ掘りは10日ほど前に掘っておいたイモを石焼きイモにして食べました。その後は、たい肥小屋のそばの巣箱からニホンミツバチの蜜を取る採蜜を体験しました。滅多に体験できないハチ蜜を絞る体験に参加者は大喜びでした。絞りながら舐めてみたハチミツの甘さに二度びっくりでした。閉講式の後も、落花生を2株掘って鈴なりの実をちぎっては大騒ぎしました。話題のつきない一日でした。 本年度2回目の保育者体験講座が10月10日(日)に行われました。この日は、園の運動会の影響があって予定した参加者も少なかったのですが、直前の欠席者が出たりして結局保育士3名、児童1名という少ない参加者になりました。研究者の方は3名そろってご参加いただきました。参加者こそ少なかったのですが、体験活動のメニュ-は盛たくさんでした。収穫体験はサツマイモ掘りに加えて里芋も収穫しました。里芋は子イモを外してバケツに入れ水を加えてイモ洗い棒を使って皮をむく体験をしました。サツマイモ掘りは10日ほど前に掘っておいたイモを石焼きイモにして食べました。その後は、たい肥小屋のそばの巣箱からニホンミツバチの蜜を取る採蜜を体験しました。滅多に体験できないハチ蜜を絞る体験に参加者は大喜びでした。絞りながら舐めてみたハチミツの甘さに二度びっくりでした。閉講式の後も、落花生を2株掘って鈴なりの実をちぎっては大騒ぎしました。話題のつきない一日でした。 |
19 | |
キウイ54個を収穫しました。(令和3年10月8日) 10月6日、キウイ54個を収穫しました。初めての収穫です。キウイは雌雄異株で植える時はセットで植えます。この苗は植えた後、樹勢が弱くて収穫にはほど遠い状態でしたが、重機で1mほど穿孔してもらって堆肥と肥料を投入し植え直したところメキメキ大きくなりました。去年、初めてピンポン玉くらいの実が5個程度つきました。今年はたくさんの実がつきましたので、5月22日、70個ほど摘果しました。摘果の仕方を知らない正平がしたことですから、それが良かったかどうかはわかりません。何回か給水をし、追肥、草刈りもしての収穫でした。実を箱に詰めリンゴを入れて成熟を待ちます。子どもたちの試食は少し先のことになります。 10月6日、キウイ54個を収穫しました。初めての収穫です。キウイは雌雄異株で植える時はセットで植えます。この苗は植えた後、樹勢が弱くて収穫にはほど遠い状態でしたが、重機で1mほど穿孔してもらって堆肥と肥料を投入し植え直したところメキメキ大きくなりました。去年、初めてピンポン玉くらいの実が5個程度つきました。今年はたくさんの実がつきましたので、5月22日、70個ほど摘果しました。摘果の仕方を知らない正平がしたことですから、それが良かったかどうかはわかりません。何回か給水をし、追肥、草刈りもしての収穫でした。実を箱に詰めリンゴを入れて成熟を待ちます。子どもたちの試食は少し先のことになります。 |
18 | |
サツマイモ一畝分試しに掘ったら、104個でした(令和3年9月28日) いよいよサツマイモ掘りのシーズンがやってきました。10月3日(日)は生活塾15班の児童がやってきます。10月12日(火)は、あさひ保育園(飯塚市川島)の年長児26名が芋掘りにきます。その後は、私立・公立の保育園、幼稚園、こども園が続々と芋掘りにきます。自園でサツマイモ栽培ができている施設も石焼きイモ作りにきたり、石焼きイモの出前を頼んでくる施設もあります。9月24日(金)、シーズン到来に備えて一畝分を試しに掘ってみました。10mの畝には苗30本を植えてあります。一畝分試しに掘ったところ大小合わせて104個の収穫でした。他の畝は、この畝より多く入っているのか、そうではないのか、気になるところです。本番の芋掘りはもうすぐです。 いよいよサツマイモ掘りのシーズンがやってきました。10月3日(日)は生活塾15班の児童がやってきます。10月12日(火)は、あさひ保育園(飯塚市川島)の年長児26名が芋掘りにきます。その後は、私立・公立の保育園、幼稚園、こども園が続々と芋掘りにきます。自園でサツマイモ栽培ができている施設も石焼きイモ作りにきたり、石焼きイモの出前を頼んでくる施設もあります。9月24日(金)、シーズン到来に備えて一畝分を試しに掘ってみました。10mの畝には苗30本を植えてあります。一畝分試しに掘ったところ大小合わせて104個の収穫でした。他の畝は、この畝より多く入っているのか、そうではないのか、気になるところです。本番の芋掘りはもうすぐです。 |
17 | |
植えたクリの木に実がなりました(令和3年9月15日) 去年、クリの苗木10本を敷地南の法面に植えました。令和2年1月26日のことでした。令和元年10月、法面の草刈りを始めたのが最初のクリ畑造りの作業でした。1m眞四角の穴を膝が隠れるほどの深さまで掘って、堆肥と肥料を投入し苗木を植えました。村瀬和彦先生のご指導にしたがって、苗木は田主丸町の栗木貴宏さんから買いました。今年の1月も更に10本の苗木を買って植えました。9月19日、職員の河中さんが初めに植えたクリの10本目に当たる晩生の利平から10個あまりの実を拾ってきました。植えてから1年8カ月しか経っていないのに大きな実をつけたのです。その大きさに職員一同、驚きました。わずか1本の苗木が実をつけただけですが、来年はどんな大きさのクリが実をむすぶだろうと今から楽しみです。 去年、クリの苗木10本を敷地南の法面に植えました。令和2年1月26日のことでした。令和元年10月、法面の草刈りを始めたのが最初のクリ畑造りの作業でした。1m眞四角の穴を膝が隠れるほどの深さまで掘って、堆肥と肥料を投入し苗木を植えました。村瀬和彦先生のご指導にしたがって、苗木は田主丸町の栗木貴宏さんから買いました。今年の1月も更に10本の苗木を買って植えました。9月19日、職員の河中さんが初めに植えたクリの10本目に当たる晩生の利平から10個あまりの実を拾ってきました。植えてから1年8カ月しか経っていないのに大きな実をつけたのです。その大きさに職員一同、驚きました。わずか1本の苗木が実をつけただけですが、来年はどんな大きさのクリが実をむすぶだろうと今から楽しみです。 |
16 | |
サツマイモの試し掘りをしました(令和3年9月9日) サツマイモの苗は、今年の5月1日に840本植えました。6月2日と5日に合わせて二番苗550本を植えました。これ以外にも300本余りを植えたので、しめて1700本を植えたことでした。ほとんどは、鹿児島県指宿市から取り寄せた紅はるか(バイオ)でした。この苗は、去年初めて300本植えたのですが、その結果が収穫量も多く味も良かったので、今年は全て鹿児島育ちの紅はるかにしました。去年の植え付けは早いもので6月16日でしたから、1カ月半早い植え付けでした。9月7日、2株を試し掘りしてみました。植え付けから4カ月と7日ですから、これからまだまだ大きくなるサツマイモですが、写真のように結構な実入りでした。この分なら豊作を期待できそうです。あとは、イノシシの襲撃に会わないように祈るばかりです。 サツマイモの苗は、今年の5月1日に840本植えました。6月2日と5日に合わせて二番苗550本を植えました。これ以外にも300本余りを植えたので、しめて1700本を植えたことでした。ほとんどは、鹿児島県指宿市から取り寄せた紅はるか(バイオ)でした。この苗は、去年初めて300本植えたのですが、その結果が収穫量も多く味も良かったので、今年は全て鹿児島育ちの紅はるかにしました。去年の植え付けは早いもので6月16日でしたから、1カ月半早い植え付けでした。9月7日、2株を試し掘りしてみました。植え付けから4カ月と7日ですから、これからまだまだ大きくなるサツマイモですが、写真のように結構な実入りでした。この分なら豊作を期待できそうです。あとは、イノシシの襲撃に会わないように祈るばかりです。 |
15 | |
クリの実が落ち始めました(令和3年8月21日) 大工小屋の裏に2本のクリが植えてあります。植えてから10年以上は経ちます。一度は切り倒されたクリの木ですが、横から芽を出して枝になって、今では、たくさんの実をつけます。今年は長雨豪雨の影響もあってか、クリの実がたくさん落ちてきました。8月21日に集めた分だけで、ざっと数えて570個くらいありました。しばらくはクリの収穫が楽しみです。今年、去年と2年続けて敷地の南端斜面に合計20本のクリ苗を植えました。早生の丹沢と晩生の利平、銀寄の3種類です。クリは自家不和合性といって、自分と同じ品種では実をつけにくい性質があります。去年植えたクリには数こそ少ないものの既に実がついています。幼児がクリ拾いできるのも、そう遠い先のことではないというクリ畑になってきました。お楽しみに。 大工小屋の裏に2本のクリが植えてあります。植えてから10年以上は経ちます。一度は切り倒されたクリの木ですが、横から芽を出して枝になって、今では、たくさんの実をつけます。今年は長雨豪雨の影響もあってか、クリの実がたくさん落ちてきました。8月21日に集めた分だけで、ざっと数えて570個くらいありました。しばらくはクリの収穫が楽しみです。今年、去年と2年続けて敷地の南端斜面に合計20本のクリ苗を植えました。早生の丹沢と晩生の利平、銀寄の3種類です。クリは自家不和合性といって、自分と同じ品種では実をつけにくい性質があります。去年植えたクリには数こそ少ないものの既に実がついています。幼児がクリ拾いできるのも、そう遠い先のことではないというクリ畑になってきました。お楽しみに。 |
14 | |
搾乳して親のヤギが元気になりました(令和3年8月16日) 8月5日、ヤギのお産が始まりました。5日に1頭、6日に2頭目が産まれましたが、2頭目は死産でした。1頭目は白毛のメスで勢いよく乳を飲み始めました。ところが、右の乳房にばかり取りついて左の乳房にはいきません。1日2日と経つうちに左の乳房は、はちきれんばかりに膨張して危ない感じになってきました。職員の正平高志さんが若いころ勤めていた農業高校での記憶をたどりながら親ヤギの搾乳を試みました。ベビーサークルを改造した木枠に、親ヤギを拉致してゆっくりと搾乳していきます。ついに、午前中に120cc、午後に250ccの搾乳に成功しました。左右の乳房は大差ないまでになりました。親ヤギの元気も回復したかに見えて職員一同胸をなでおろしたことでした。何十年も前の記憶が役に立ったヤギの搾乳でした。 8月5日、ヤギのお産が始まりました。5日に1頭、6日に2頭目が産まれましたが、2頭目は死産でした。1頭目は白毛のメスで勢いよく乳を飲み始めました。ところが、右の乳房にばかり取りついて左の乳房にはいきません。1日2日と経つうちに左の乳房は、はちきれんばかりに膨張して危ない感じになってきました。職員の正平高志さんが若いころ勤めていた農業高校での記憶をたどりながら親ヤギの搾乳を試みました。ベビーサークルを改造した木枠に、親ヤギを拉致してゆっくりと搾乳していきます。ついに、午前中に120cc、午後に250ccの搾乳に成功しました。左右の乳房は大差ないまでになりました。親ヤギの元気も回復したかに見えて職員一同胸をなでおろしたことでした。何十年も前の記憶が役に立ったヤギの搾乳でした。 |
13 | |
真夏のシイタケ畑(令和3年8月12日) 真夏のシイタケ畑に横積みして、仮伏せしたホダギ48本があります。このホダギは、昨年(令和2)12月21日に生活体験学校敷地南側法面に植えたクヌギを伐採して玉切りしたものです。伐採したまま、その場で乾燥させていたのですが、2月20日、生活文化交流センターに運んでコマ打ちしました。梅雨明けには本伏せしないといけなかったのですが、少し遅れて8月1日職員作業でホダギを移し替えました。本伏せとは、シイタケの菌糸を原木に蔓延させるために原木を立てることをいいます。この作業で古くなって朽ちたホダギをリヤカー4台分撤去しました。この朽ちたホダギにカブトムシが集まります。子どもの関心の的でもあります。 真夏のシイタケ畑に横積みして、仮伏せしたホダギ48本があります。このホダギは、昨年(令和2)12月21日に生活体験学校敷地南側法面に植えたクヌギを伐採して玉切りしたものです。伐採したまま、その場で乾燥させていたのですが、2月20日、生活文化交流センターに運んでコマ打ちしました。梅雨明けには本伏せしないといけなかったのですが、少し遅れて8月1日職員作業でホダギを移し替えました。本伏せとは、シイタケの菌糸を原木に蔓延させるために原木を立てることをいいます。この作業で古くなって朽ちたホダギをリヤカー4台分撤去しました。この朽ちたホダギにカブトムシが集まります。子どもの関心の的でもあります。 |
12 | |
| クリ畑の作業道を広げてもらいました(令和3年8月9日) 生活体験学校のクリ畑には去年1月に植えたクリの木が9本あります。その下(下段)には今年の1月に植えたクリの木が10本あります。クリの苗木には肥料よりも水やりが大切と言われています。特に1年目は手を抜いてはいけません。7月24日(土)九州大学社会教育主事講習の受講生14名が、社会教育実践演習の一環としてクリ畑の作業道を広げる作業をしてくれました。肥料を入れたり水をやったりする作業には足元が大切です。ツルツル滑る斜面の作業よりも50mの水平道が東西に走っていると仕事もはかどります。毎年、九州大学社会教育主事講習の受講生のみなさんには助けてもらっています。 |
11 | |
ニホンミツバチの採蜜2回(令和3年7月30日)  7月18日、クリの巣箱を開いてみたらハチに逃げられていました。やむなく、蜂のいない巣箱の1段目を取り出したところ、残された蜜の量が4.2㎏ありました。7月24日、食育キッズ(野菜作り)のプログラムとしてサクラの巣箱の一段目の箱を開いたところ、蜂蜜の量が5.7㎏ありました。クリの巣箱は、クリの木の根元に置いた巣箱のことで、サクラの巣箱は去年から2回採蜜した一番古い巣箱のことです。クリの巣箱はハチの出入りが急になくなったので、様子を見ようと開いたものでした。ハチが逃げ出した理由は、今のところ分かりません。サクラの巣箱は、そろそろ蜜が溜まったころだろうと予測して開いた予定の採蜜でした。 7月18日、クリの巣箱を開いてみたらハチに逃げられていました。やむなく、蜂のいない巣箱の1段目を取り出したところ、残された蜜の量が4.2㎏ありました。7月24日、食育キッズ(野菜作り)のプログラムとしてサクラの巣箱の一段目の箱を開いたところ、蜂蜜の量が5.7㎏ありました。クリの巣箱は、クリの木の根元に置いた巣箱のことで、サクラの巣箱は去年から2回採蜜した一番古い巣箱のことです。クリの巣箱はハチの出入りが急になくなったので、様子を見ようと開いたものでした。ハチが逃げ出した理由は、今のところ分かりません。サクラの巣箱は、そろそろ蜜が溜まったころだろうと予測して開いた予定の採蜜でした。 |
10 | |
| サツマイモ苗の定植が終わりました(令和3年7月20日) 生活体験学校の北の菜園は全面サツマイモの苗でいっぱいになりました。今年は植え付けの仕方を変えて、全面サツマイモを植えました。苗は紅はるか(バイオ)がほとんどです。生産地は鹿児島県指宿市開聞十町のまつざわ農園です。職員の矢野さんが取り寄せてくれました。利用者の持ち込み苗が2種類、約100本程度ありましたが、指宿市からの苗が約1000本、この苗から採取した二番苗が約700本です。全部で1800本の苗に園名を書いた札がずらりと立っています。あなたの園の名札も立っているはずです。電話のお問い合わせはご遠慮ください。 |
9 | |
| 子ヤギが2頭やってきた(令和3年7月12日) 今、生活体験学校に居るオスのヤギは、直方市の清野さんにお借りしていたものです。間もなく、生活体験学校のメスのヤギに子ヤギが産まれます。6月30日、清野さんがオスのヤギを引き取りに来てくれました。メスのヤギ一頭だけになると、生活体験学校はさみしくなるので、赤ちゃんヤギが産まれるまで貸してあげようと子ヤギ2頭を軽トラックに積んで連れてきてくれました。今年3月に生まれたばかりの子ヤギです。一頭はメスで、体全体が黒っぽい毛ですが、特に首と顔全体が黒い毛におおわれています。もう一頭はオスで頭から首すじにかけて茶色の毛が走っています。かわいい子ヤギたちです。 |
8 | |
5つの団体がジャガイモを掘った(令和3年6月28日)  宣言明けを待っていた子どもたちがジャガイモ掘りにやってきた。6月22日に、おひさま。6月24日に、庄内保育園。6月26日に、食育キッズ。6月27日に、生活塾3班と保育者体験講座。4日間に5つの団体がジャガイモ掘りをしたのは今年が初めてだった。一番多く掘ったのは、庄内保育園だった。コロナがなければもう少し早くジャガイモ掘りができたのだが、20日までは施設利用がコロナの感染防止のためできなかった。収穫量は職員が予想した量より多かった。子どもたちが喜んだのは言うまでもない。 宣言明けを待っていた子どもたちがジャガイモ掘りにやってきた。6月22日に、おひさま。6月24日に、庄内保育園。6月26日に、食育キッズ。6月27日に、生活塾3班と保育者体験講座。4日間に5つの団体がジャガイモ掘りをしたのは今年が初めてだった。一番多く掘ったのは、庄内保育園だった。コロナがなければもう少し早くジャガイモ掘りができたのだが、20日までは施設利用がコロナの感染防止のためできなかった。収穫量は職員が予想した量より多かった。子どもたちが喜んだのは言うまでもない。 |
7 | |
フェンスにぶらさがった巨大カボチャ(令和3年6月14日)  南の菜園の南端にあるフエンスに職員の河中さんがカボチャのツルを這わせました。この場所は、落ち葉囲いと呼んで野菜の収穫後の土や根や枯れ草を積み上げてきた所です。土をふるって畑に返したり、十分に枯れた枝や草は取り出して燃やします。囲いを解いて何年分かの養分タップリの土をならしてカボチャの苗を植えたのですから、巨大カボチャがフェンスにぶら下がったというわけです。目盛りをあてがったら18センチもありました。 南の菜園の南端にあるフエンスに職員の河中さんがカボチャのツルを這わせました。この場所は、落ち葉囲いと呼んで野菜の収穫後の土や根や枯れ草を積み上げてきた所です。土をふるって畑に返したり、十分に枯れた枝や草は取り出して燃やします。囲いを解いて何年分かの養分タップリの土をならしてカボチャの苗を植えたのですから、巨大カボチャがフェンスにぶら下がったというわけです。目盛りをあてがったら18センチもありました。 |
6 | |
| 保育園でミツバチを取りました (令和3年6月7日) 21日(金)の昼前、飯塚市仁保の愛の光保育園の佐藤園長から園庭の桜の木に分蜂したニホンミツバチが群がっているという報せがはいりました。職員の河中さんと矢野さんの二人が支度をして捕獲に向かいました。大きなビニール袋に蜂の大部分を取り込みました。生活体験学校に持って返って、堆肥小屋の陰に置いてあった空きの巣箱に移し込みました。正平高志さんも応援にかけつけて、今年3つ目の巣箱にニホンミツバチを確保しました。巣箱は合計4つになりました。果たして今年の採蜜はうまくいくでしょうか? |
5 | |
| 分蜂したニホンミツバチ (令和3年5月31日) ひとつの巣に新しい女王蜂が生まれると、古い女王蜂は約半分の働き蜂を連れて引越しを始めると言われています。これを分蜂(ぶんぽう)と言います。生活体験学校の「桜の巣箱」では、5月9日と13日の二度分蜂しました。分蜂の群れを捕獲できればハチ蜜を取る量が増えるのですが、二つとも取り逃がしました。三度、四度と分蜂することもありますので、次の分蜂は捕獲したいものです。 |
4 | |
サツマイモの苗800本を植えました(令和3年5月24日) 5月1日、生活体験学校の北の菜園にサツマイモの苗800本を植えました。一度に800本のイモ苗を植えたのは初めてのことでした。苗は紅はるか(バイオ)でした。苗の生産地は鹿児島県指宿市で、開聞岳のすぐ近くです。職員の矢野さんが取り寄せてくれました。 |
3 | |
キウイの花がたくさん咲きました (令和3年5月10日) 5月6日、敷地の東南に植えたキウイがたくさんの花をつけました。去年、初めて小さな実を5つほどつけたキウイですが、ピンポン玉より小さいものでした。雌株の花が多くて、雄株の花が少ないのですが、ニホンミツバチが蜜を求めて飛んできました。今年、食べられるような実がなるでしょうか?楽しみです。 |
2 | |
スズメバチを退治しています(令和3年5月18日) 今年のニホンミツバチの巣箱は3つです(去年は1つでした)。ミツバチの大敵スズメバチが出始めました。巣箱のすぐ近くにハチ取り器を取りつけていますが、5月7日、3つのハチ取り器で計17匹のスズメバチを取りました。17匹のうち12匹が間もなく卵を産むと思われる大きな女王バチでした。(大成功でした!) |
1 | |